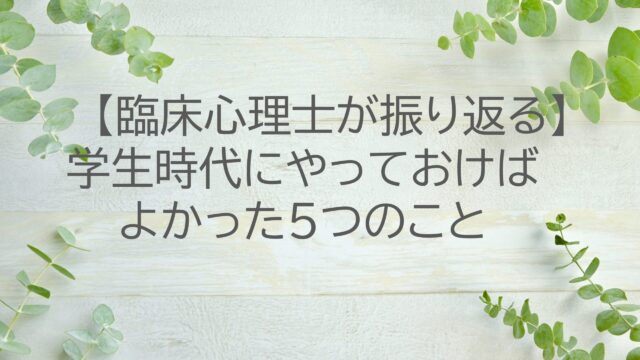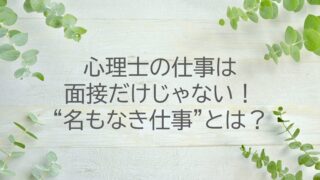心理臨床に欠かせない言語化の力|院生時代に学んだこと
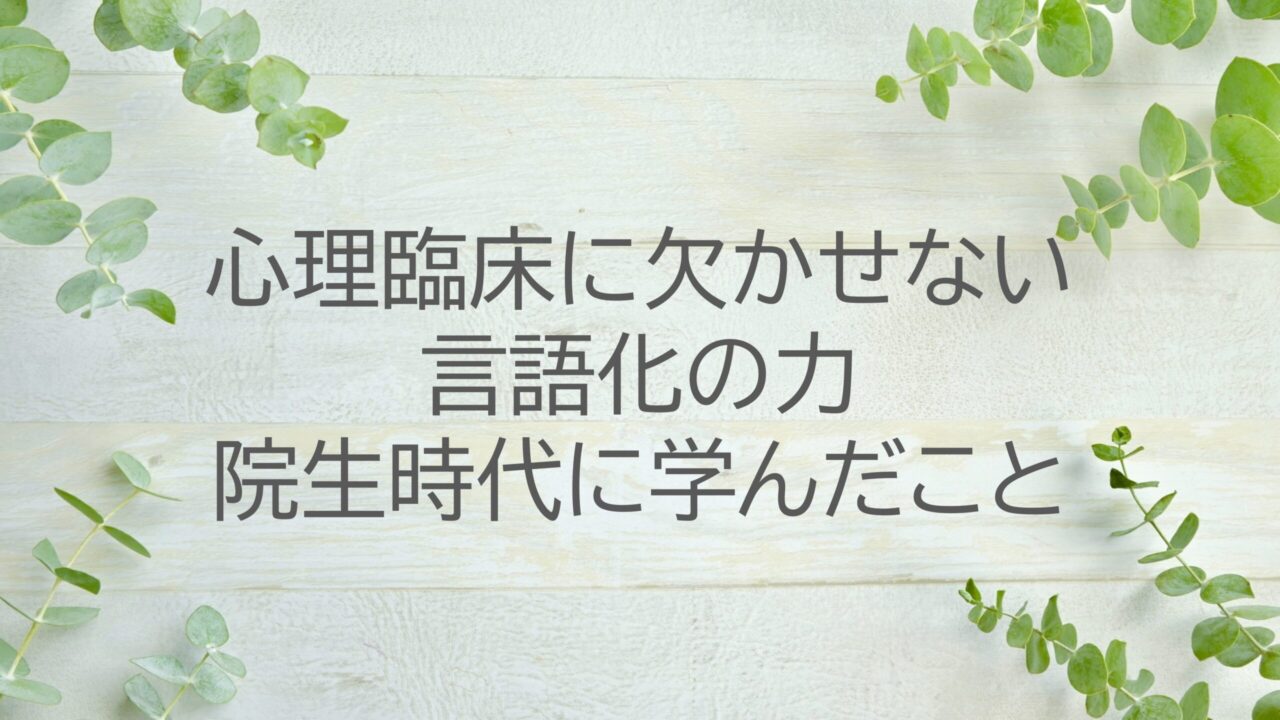
※本記事にはプロモーションが含まれています。
大学院に進学し、本格的に心理臨床の道を歩み始めたとき、私は自身の言語化する力の乏しさに、大きな壁を感じていました。
心理臨床を学び始めた院生や若手心理士の方なら、きっと同じ悩みを抱えているのではないでしょうか。
だからこそ、この記事を開いたのでしょう。
この記事では、言語化に苦労した私の実体験をもとに、どのようにして言語化の力を鍛えてきたのか、その例をご紹介します。
言語化に苦労した大学院時代
 心理学部の授業では、知識のインプットと概念の理解が中心でしたが、臨床の現場、そして院のゼミやケースカンファレンスで求められるのは、学んだ知識を血肉化し、「あなたはどう考え、どう感じるか」を適切かつ的確な言葉で表現することでした。
心理学部の授業では、知識のインプットと概念の理解が中心でしたが、臨床の現場、そして院のゼミやケースカンファレンスで求められるのは、学んだ知識を血肉化し、「あなたはどう考え、どう感じるか」を適切かつ的確な言葉で表現することでした。
当時の私にとっては、頭の中ではぼんやりと感じていても、それを端的で適切な言葉にして表現するのは、とてつもなく難しかったのです。
発言の機会を与えられると、しどろもどろになり、言葉を紡ぎ終えても「どうもしっくりこない」「言いたいことの半分も伝わっていない」という強い不全感だけが残りました。
最後に先生の総括を聞いたとき、「ああ、まさにそれが言いたかった!」と胸がスッと軽くなる。
それと同時に、帰り道には「どうして先生のようにすぐ言葉にできないのだろう」と落ち込む日々でした。
当時、とっさに出てくる言葉は「ヤバい」「すごい」の2語レベル。
便利な一方で情報量の少ない言葉ばかりでした。
今振り返れば、学部時代にもっと言葉を丁寧に扱い、その微細なニュアンスを大切にする訓練をしておくべきだったと強く後悔します。
もし、時間を遡って当時の自分に助言できるなら、こう伝えたいです。
- 「丁寧に、忠実に、繊細に使えるボキャブラリーを増やしなさい」: 感情や状況のグラデーションを表すための言葉を意識的に収集すること。
- 「言葉の引き出しを整理し、いつでも取り出せるように準備しなさい」: 知識として知っているだけでなく、とっさに使える実用的な語彙として頭の中で分類・整理すること。
言語化の力を鍛える方法|心理臨床に役立つ用例採集
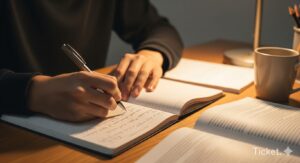
でも、嘆いてばかりいても力はつきません。
持っていない能力は、意識的な努力によって身につけていくしかありません。
そこで私が取り組んだのが「用例採集」でした。
自分の言語化能力の乏しさに絶望して以来、私はひたすらこの作業を続け、どうにか今のレベルまでたどり着きました。
今でも諸先輩方の書籍や講演を聞いて自分の語彙力のなさに落ち込むことはありますが、同時に新しい「用例」を発見できた喜びでワクワクもします。
この「用例採集」という言葉を知ったのは、三浦しをんさんの小説『舟を編む』(2011年刊行)がきっかけです。
文庫本版や最近ではNHKでドラマ化もされました。
この辞書編集をテーマにした物語の中で、「用例採集」という表現に出会いました。
「用例採集」とは、辞書編集者たちが辞書に載せるための言葉の実例を集める作業を指します。
ここで私が言う「用例採集」とは、自分の中の「臨床家としての辞書」に言葉を追加していく作業のことです。
具体的には、以下のような行動を日々実践することです。
1.臨床・学習現場からのライブ採集
- 指導教員やスーパーバイザーの金言の記録: ケースカンファレンスや授業中に先生が発した、クライエントの感情や状況を端的に、かつ深く表現しているフレーズや、介入の意図を明確にする専門用語の適切な使い方を、すかさずメモする。
- 先輩や同期の表現の観察: 先輩や同期が、クライエントの状況を説明する際の表現や、応答の際の言葉遣いの機知に富んだ一言、ユーモアの使い所などを記録する。
2.メディア・文献からの意識的収集
- 専門書籍・論文の精読と書き抜き: 専門領域の書籍や論文を読む際、内容の理解だけでなく、表現技法や概念の定義の仕方に注目し、心に響いた表現や、自分の感覚を代弁してくれるような言葉を抜き出して記録する。
- 質の高い文章を読む: 心理臨床の所見や情報提供書、報告書といったプロフェッショナルな文書を読む機会があれば、他の人の書き方の構成や表現を参考に「用例採集」を行う。
とにかく、自分の身の回りにある「いいな」と感じた言葉を何でもメモしていきます。
この採集した「用例」は、すぐには自分の言葉として使えなくても、繰り返し触れることで、いつか必ず自分の血肉となり、必要な瞬間に「引き出し」から取り出せるようになります。
話す力と書く力の両輪
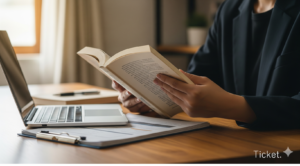
心理臨床において言語化の力は、「話す力」(面接・対話・カンファレンス)と「書く力」(所見・記録・報告書)の両輪で成り立っています。
話すのは得意なのに、文章にすると途端に言葉が出てこなくなるという人もいるでしょう。
心理臨床の分野では、所見や情報提供書を作成する際に、この壁にぶつかりやすいかもしれません。
もしあなたがそう感じるなら、たくさんの活字を読みましょう。
まずは、小説に親しんでみてください。
豊かな表現に数多く出会うことができます。
また、他の人が書いた所見や報告書を読む機会があれば、
他の人の書き方を参考に「用例採集」をするのも非常に有効です。
私は、学部時代は軽く考えていた「言葉」というものの重みを、年々強く感じるようになりました。
特に心理臨床では、言葉に込められた微細なニュアンスをとても気にする必要があります。
それは、感性で相手と向き合い、言葉でそれを共有する文化だからだと思います。
語感を育てる辞書との出会い
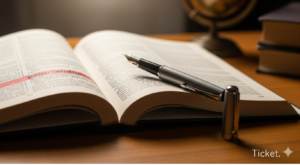 言葉のニュアンスをより深く理解したいとき、私の支えになっている一冊があります。
言葉のニュアンスをより深く理解したいとき、私の支えになっている一冊があります。
岩波書店から出版されている中村明著『日本語 語感の辞典』です。
似ているけれど微妙に意味が異なる語の違いが、丁寧に解説されています。
行き詰まったときに開くと、自分の思いをより適切に表す言葉に出会え、語彙の奥行きが広がっていくのを感じます。
まとめ ― 言葉に悩むのは成長の第一歩
心理臨床という道を選んだ私たちは、言葉という最も身近でありながら、最も奥深い道具を駆使して、人の心と向き合います。
だからこそ、心理臨床を学ぶ方の多くが、「言語化の難しさ」という壁に直面するのではないでしょうか。
むしろ、この壁にぶつかることは、成長のために必要不可欠なことだと私は思います。
言葉を丁寧に紡ぎ、感性をもって相手に伝えること。
それは心理臨床における文化であり、専門職としての根幹でもあります。
この壁を感じたこと自体が、成長への第一歩を踏み出した証だとも思います。
もし、その一歩を踏み出せたのなら、あとはその力をつけていくだけです。

そのためのポイントを改めて以下にまとめます。
- 用例採集を習慣にすること
- いろいろな種類の活字に触れること
- 言葉の語感を常に意識すること
あなたは普段どんな方法で言葉を蓄えていますか?
この記事が、みなさんの言葉の引き出しを少しでも豊かにするきっかけになれば嬉しいです。