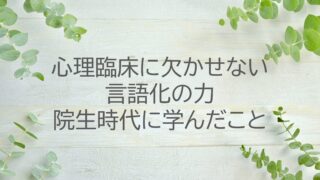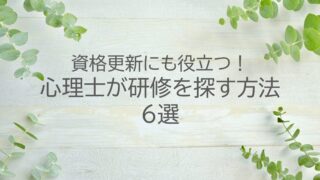若手心理士のためのセルフケア:心と体を守り、臨床を豊かにする|おすすめ書籍4選

※本記事にはプロモーションが含まれています。
新年度が始まり、早くも半年が経ちました。
新社会人の心理士の皆さんは、職場の雰囲気に慣れつつも、疲れを感じ始めている頃かもしれません。
心理職として日々、クライエントの心に寄り添い、深く関わる中で、知らず知らずのうちに心身に負担がかかっていることは少なくありません。
燃え尽き症候群や二次受傷の可能性は、常に私たちのすぐそばにあるものです。
そうした中で、セルフケアは、私たちが心理職としての実践を長く続けていくために欠かせないスキルです。
だからこそ、セルフケアを「特別な時間」ではなく、「仕事を続けるための基盤」として大切にしたいと思っています。
本記事では、若手心理士の皆さんが実践できる色々なセルフケアの方法を、おすすめの書籍とともにご紹介します。
みなさんの日々の臨床に役立つヒントがみつかれば幸いです。
なぜセルフケアが重要なのか?
 心理職の仕事は、クライエントさんの苦悩や葛藤に触れることが多く、それにより心理的影響を受けることもあります(いわゆる二次受傷)。
心理職の仕事は、クライエントさんの苦悩や葛藤に触れることが多く、それにより心理的影響を受けることもあります(いわゆる二次受傷)。
また、倫理的な責任や守秘義務も常に伴います。
これらの要因が重なり、セルフケアを怠ってしまうと、自身のメンタルヘルスが損なわれ、結果としてクライエントさんへの支援の質にも影響が出てしまうかもしれません。
セルフケアは、こうしたリスクから自分自身を守るだけでなく、クライエントさんを守り、自己一致した状態で臨床に臨むために重要なスキルの一つです。
自分が安定しているからこそ、クライエントさんに対して真摯に向き合い、安定した支援を提供できるのです。
おすすめ書籍から学ぶセルフケア実践法
ここからは、色々なセルフケアの方法を、4つの書籍を元にご紹介します。

1.先輩カウンセラーの知恵に学ぶ:伊藤絵美著『カウンセラーはこんなセルフケアをやってきた』
まずは、先輩カウンセラーが実践してきたセルフケアの具体例を知ることから始めましょう。
伊藤絵美氏著の『カウンセラーはこんなセルフケアをやってきた』は、タイトルが示す通り、カウンセラーがどのようにして自身の心を守り、ケアしてきたのかが詰まった一冊です。
CBTを専門とする著者がマインドフルネスや認知再構成法、スキーマ療法を自身に実践する中で培ったセルフケアの各種が紹介されています。
CBTのエッセンスに親和性の高い方は、この本で紹介されている方法をピックアップし、試してみると良いかもしれません。
特に最近の傾向として、CBTの視点や手法は、面接中のスキルのレパートリーとして必須と言っても過言ではありません。
身をもって実践し、その効果を体感することで、ケースフォーミュレーションや心理教育にリアリティが増し、臨床の力としても定着していくことでしょう。
最初はうまくいかなくても、試行錯誤を繰り返すことで、自分にとって効果的なセルフケアを見つけやすくなります。

2.ACTで心の柔軟性を高める:武藤崇著『ACT 不安・ストレスとうまくやる メンタルエクササイズ』
次に紹介するのは、アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)に基づいたセルフケアの実践的なエクササイズ集です。
本書では、心配や不安、ストレス等は、ある感情や思考に心が「フック」されている状態だとし、「フック」されている状態だということにまずは気づけること、そのうえで、その感情や思考と上手に距離をとることの重要性について、わかりやすく解説されています。
この本では、そのためのエクササイズが多数紹介されています。
エクササイズは短時間で実践できるものが多く、挿絵も豊富で視覚的にも理解しやすい構成です。
疲れた日でも、5分ほどの時間で取り組めるものが多いのも魅力です。
呼吸に意識を向けるマインドフルネスや、自分の価値観を明確にするワークなど、心の状態を客観的に観察し、感情に巻き込まれない力を養うための実践的な方法が満載です。
「不安があること自体を否定しない」ことを大切にしながら、日々の臨床で感情に圧倒されそうになった時、これらのエクササイズは心の安定を取り戻す助けになると思います。
3.ストレス耐性を育む:浅井咲子著『不安・イライラがスッと消え去る「安心のタネ」の育て方』
 続いては、日々の生活の中でストレスに上手に対処し、心の回復力を高めるためのセルフケアです。
続いては、日々の生活の中でストレスに上手に対処し、心の回復力を高めるためのセルフケアです。
この本は、ポリヴェーガル理論に基づき、レジリエンス(心の回復力)を高め、安心して生きていくためのヒントを与えてくれる一冊です。
「安心のタネ」という比喩を使いながら、日常生活の中でできる安心感の育て方が具体的に紹介されています。
本書の魅力は、日常生活で当たり前にしている動作に目を向けられること、そこから安心感を育てていくことに重点を置いているので、どのコツもすぐに実践しやすいことです。
神経の成り立ちを理解して、認知よりも身体から整えていくアプローチは、理屈より感覚で理解しやすく、効果的です。
私がよく実践しているコツは「脳幹にタッチする」や「お腹を手のひらで温める」です。
若手心理士の皆さんにとって、臨床のプレッシャーや責任は大きなストレス源となり得ます。
この本は、日々の小さなスイッチの切り替え方のコツを見つけ、それによって「安心のタネ」を育てていくことの重要性を教えてくれます。
4.悲しみと向き合う力を育む:水澤都加佐著『悲しみにおしつぶされないために:対人援助職のグリーフケア入門』
最後に、悲しみや喪失といった避けられない感情と向き合うためのセルフケアです。
心理職として、クライエントの悲しみや喪失に直面することは避けられません。
時には、喪失による悲しみ等、自分自身も辛い気持ちになることがあるでしょう。
気づかぬうちに感情に蓋をして乗り越えようとして、心がすり減り、臨床を続ける活力がなくなってしまうことだってありえます。
無理にポジティブになろうとするのではなく、悲しい感情があることを認め、感情の居場所を作ってあげることが重要です。
この本のおすすめポイントは、「グリーフワークのチェックポイント」「境界線・チェック」「ディタッチメント・チェック」「セルフケアチェック」が掲載されていることです。
これらのチェック項目は、自身の置かれている状況を俯瞰的、体感的に捉えなおすのに役立ちます。

まとめ
ご紹介した4冊の本は、それぞれ異なる視点からセルフケアの重要性とその実践方法を教えてくれます。
心理士としての活動を支え、一人の人間としての自分を整えるヒントが満載です。
セルフケアは、一度やれば終わりというものではありません。
日々の臨床と生活の中で、意識的に継続していくことが何よりも大切です。
そして、感情を否定したり押し込めて蓋をすることは、かえって心の健康を害してしまうことの方が多いです。
ポジティブな感情もネガティブな感情も、どちらが良くてどちらが悪いという性質のものではありません。
それぞれの感情にはそれぞれの居場所が必要です。
どの感情も同様に大事なものとして認め、置いておけるようになることがセルフケアのコツ、と言っても過言ではありません。
セルフケアは、あなたの臨床をより豊かにし、心理職としてのキャリアを長く継続するための強力な味方となります。
若手心理士の皆さんが、健やかに、そして信念を持って臨床に励めるよう、心から応援しています。


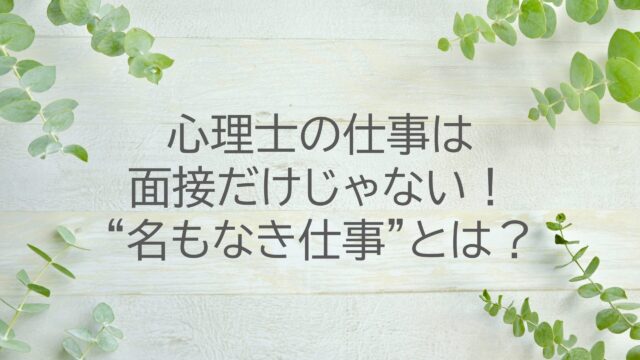
-640x360.jpg)