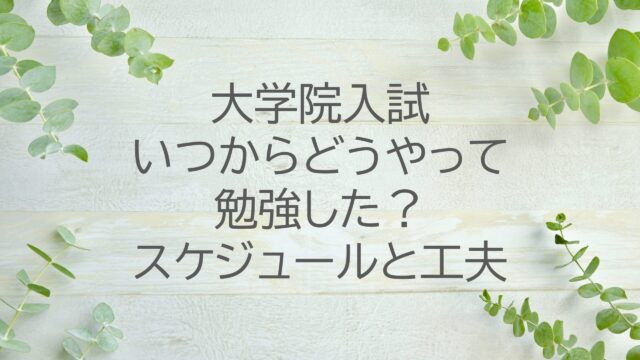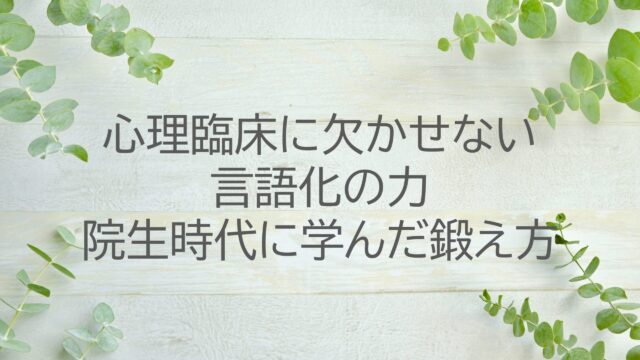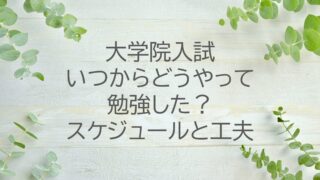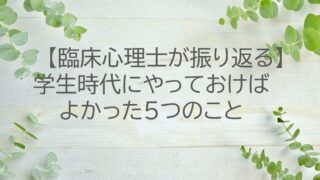心理学部生のための体験談|やっててよかった5つのこと
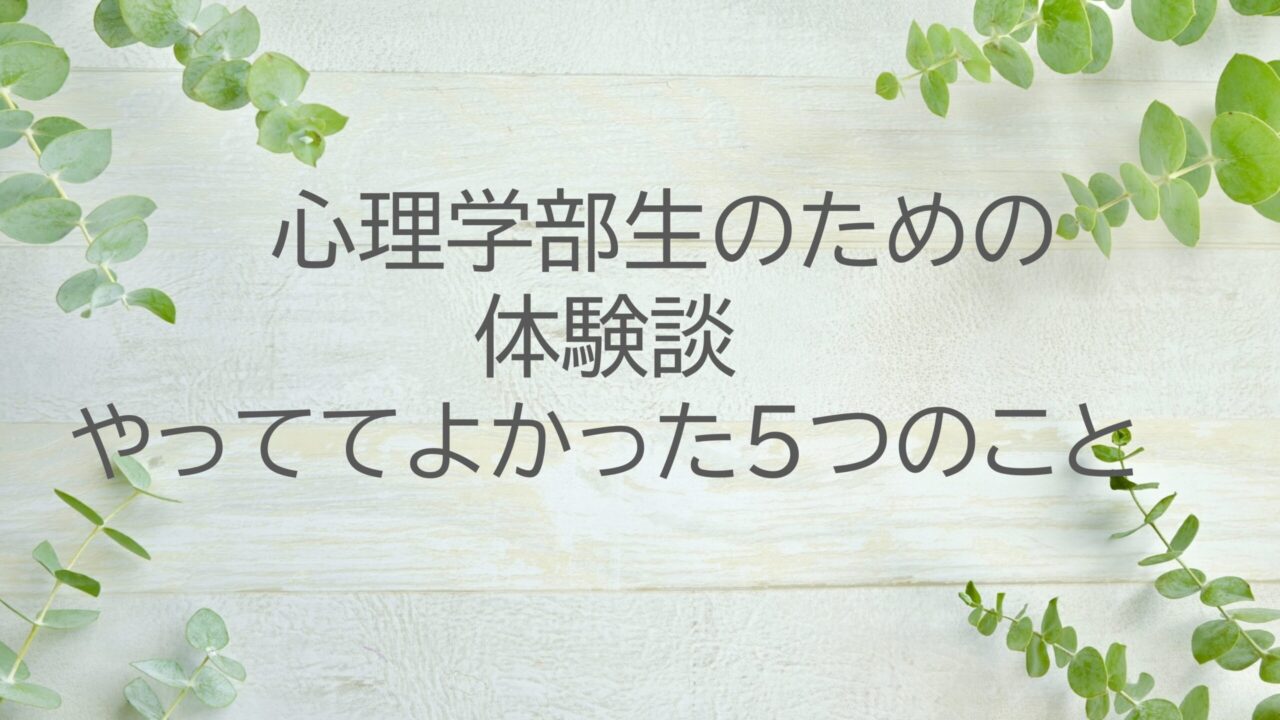
心理学部に通っていた頃、「この行動って、将来の役に立つのかな?」と半信半疑でいろんなことに挑戦していました。
いつも手探りで、正直「カウンセラーになるために意味があるのかな」と思うことも多かったです。
でも数年たった今、現場で働いたり、資格試験の勉強をするなかで、
「あのときの経験が、思いがけず自分の支えになっていたな」と感じる場面がたくさんあります。
この記事では、私が心理学部時代に実際にやってみて、「やっておいてよかった」と思った行動をいくつか紹介します。
すごく特別なことではなく、ふとしたきっかけで始めたことばかりですが、
今ふり返ると、それぞれが自分をつくる大事なプロセスだったなと思います。
なお、日々の勉強習慣についてはこちらの記事にまとめています。合わせてご覧いただけますと幸いです。
▶︎ 資格試験にも役立つ!心理学部時代にやってよかった5つの勉強習慣|未来の自分に感謝された工夫たち
心理系以外のバイトをしてみる

学部生の頃、私は心理に関係のあるアルバイトではなく、飲食店やアパレル販売など、一般的な接客の仕事をいくつか経験しました。
当時は「心理に直接関係ないし、意味あるのかな」と思うこともありましたが、今ふり返ると、“世の中の職場の空気”を肌で感じられた経験はすごく大きかったです。
例えば、「この仕事量でこの時給って、実際どう感じる?」とか、「忙しい時間帯に指示がうまく伝わらないと現場はどうなるか」など、机上の知識ではわからなかったことを、自分の体で知ることができました。
また、学生という“守られた立場”を離れて、組織の一員として責任をもって働くという経験も、私にとっては新鮮で貴重なものでした。
自分の都合ではなく、シフトやルールに合わせて動く。上司や同僚との関係の中で、自分の役割を果たす。
そうした経験は、のちに心理職として「組織に属しながら働く」ことの土台にもなっていきました。
心理士を目指す学生の多くは、ビジネスマナーを学ぶ機会があまり多くありません。
そのため、こうしたアルバイトを通じてビジネスマナーを実践的に学べたことは、本当に貴重でした。
知識として知っていても、現場で実際に言葉遣いや電話対応、報連相のやり方を体験できるのは全く別物。
この経験が就職活動や心理職として働き始めた後にも大いに役立ちました。
心理職として働く中で、さまざまな業種・職種の人と関わることがあります。
話を聴くとき、相手とまったく同じ経験をすることはできませんが、自分の経験の幅があれば、そこから想像し、共感の手がかりを探ることができます。
バイトをしていなければ、私はおそらくその“ツール”をあまり持っていなかったと思います。
お金を稼ぐってどういうことか。現場で人と動くってどういうことか。
それらを、心理とは別の角度から体感しておいたことは、今でも自分の軸の一部になっています。
いろんな人と話してみる

学部時代、心理学部以外の人も含めて、いろんな人と深く話す機会があったことは、今になっても心に残っている経験のひとつです。
同じ心理学部の友人とはもちろん、サークルやアルバイト先で出会った人たち、または先生方とも、何度もいろんな話をしました。
将来のこと、家族のこと、自分の好きなこと、悩みごと……。
損得や正解・不正解を求めるのではなく、ただ「その人のことを知りたい」と思って聴く時間が、私にとってはとても貴重でした。
心理学を学ぶ前に、ひとりの人として、相手の話にちゃんと耳を傾け、語り合える関係性を体験できたこと。
それは後々、心理職としての在り方を考えるときに、静かに自分のベースになっていたように思います。
また、自分とは異なる価値観や人生観に触れたことで、「こういう見方もあるんだ」と、少しずつ自分の視野が広がっていく感覚もありました。
人の話を聞くこと。
その奥には、「この人はどんな世界を生きてきたんだろう」と思う気持ちがある。
そんな原点のようなものに触れられたことが、学生時代の大きな学びでした。
研究協力に積極的に参加する

学部時代、先輩や大学院生の研究協力に参加する機会がありました。
正直、最初は「研究って難しそう」・「なんだかハードルが高いな」と感じていて、なかなか踏み出せずにいました。
しかし、質問紙や心理検査の被験者、インタビュー調査の被験者など、さまざまなデータ収集の方法を体験することができたため、研究の全体像や流れが具体的にイメージしやすくなりました。
この経験があったことで、いざ自分の卒業論文や修士論文を計画する際にも、何をどう進めればいいかが見えやすく、スムーズに取り組むことができました。
また、研究協力の場で、自己理解を深めたり、自分の関心のある心理療法やテーマに出会えたのも大きな収穫でした。
机上の勉強だけでは得られない、貴重な実体験だったと思います。
学会に参加してみる

学部生でも参加できる学会は意外と多く、私も友人と一緒に“ちょっとした旅”のような感覚で参加したことがあります。
実際に足を運んでみると、論文や教科書だけでは触れられない、最前線の研究や実践的な取り組みに触れられる貴重な機会でした。
もちろん、発表の内容すべてを理解するのは難しいこともありますが、それでも「今、どんな問いが立てられ、どんな視点から研究が行われているのか」にふれるだけでも、大きな学びになります。
ポスターや口頭発表を拝聴する中で、自分の関心が少しずつ明確になっていき、研究テーマを考える上でもとても参考になりました。
学会は、情報収集や視野を広げるだけでなく、心理学を学ぶことそのものへのモチベーションを高めてくれる場でもあります。
最初はわからないことばかりでも、そうした空気に身を置いてみること自体が、大きな一歩になったなと感じます。
心理系のボランティアや実習に参加する
学部生のうちに心理系のボランティア活動や実習に参加できたことは、とても貴重な経験でした。
初めて現場に行ったときは、今まで勉強してきたことがなかなか活かせず、正直落ち込んだこともありました。
しかし、医療、教育、福祉などの現場のリアルな雰囲気を肌で感じることで、「この場所で自分にできることは何だろう」「どんな役割が求められているんだろう」と、少しずつ考えられるようになりました。
現場では、理論だけでは説明しきれない人と人との関わりや、コミュニケーションの難しさに直面することも多くあります。
そうした体験を通して、「心理職としてどんな道を歩みたいのか」がより具体的に見えてきて、進路選択にも大きな影響を与えました。
また、現場の空気感を知ったうえで勉強を続けることで、机上の知識と実際の現場が結びつき、学びへのモチベーションも自然と高まったように思います。
さらに、実習やボランティアのあとには、困ったことや感じたこと、勉強になったことをメモしておくようにしていました。
あとから見返すと、自分の成長を実感できるのが嬉しかったですし、その中で見つけた自分の“癖”や思考のパターンは、今でも臨床の現場で気をつけるべきポイントとして役立っています。
そして数年後、実習指導をする立場になったとき、「自分も初めての実習ではこんなことを不安に思っていたな」と、当時の記録を読み返して実習生の気持ちを思い出すことができたのも、大きな助けになりました。
まとめ
どんな経験も、それ自体が「結果」ではなく、成長していくプロセスの一部です。
大切なのは、その時々の体験に自分なりの意味を見出し、過去の自分の試行錯誤を、今の自分の糧として活かしていくことだと感じています。
この記事でご紹介した内容がすべての方に当てはまるわけではありませんが、日々の学びや実践の中に、将来の専門性を育む芽は存在していると思います。
目の前の経験を丁寧に受けとめながら、自分自身の歩みを大切に重ねていきたい。
そんなことを心の片隅に置きながら、これからも学びを続けていけたらと思います。