心理面接への陪席は、心理士としての成長にとって非常に貴重な機会です。
特に初めての陪席では、「何を意識すれば良いのか」「どう振る舞うべきか」戸惑うことも多いでしょう。
ただそこに“いる”だけでなく、「どのようにそこにいるか」によって、得られるものは大きく変わります。
この記事では、初学者の皆さんが陪席から多くのことを学び、実りある経験とするための6つのポイントをお伝えします。

五感をフル活用し、面接の「空気感」を感じ取る
心理面接は、言葉のやり取りだけでなく、その場の空気感が非常に重要です。
セラピスト(Th)とクライエント(Cl)の間に流れる微細な感情の動き、緊張、安堵、沈黙の意味など、頭だけではなく身体全体で、五感を使って丁寧に味わってみてください。
クライエントさんの声のトーン、表情、視線、身振り手振り、そして空間全体の雰囲気…。
これらは記録に残らない情報ですが、面接の深層を理解するための鍵となります。
記録に集中しすぎず、「いま、ここ」で起こることを体感する
「一言一句聞き漏らすまい」と記録に集中しすぎてしまうのは、初学者によくあることです。
もちろん記録は大切ですが、それ以上に重要なのは、その場で展開される面接のリアルタイムな流れを体感することです。
セラピストの質問の意図、クライエントさんの反応、そしてそれらがどのように面接を動かしていくのか、「いま、ここ」で起きていることに意識を向けてみましょう。
ただし時折、セラピストから「逐語で記録をとってほしい」と依頼されるケースもあるようです。
たとえば、その記録をSV資料として活用したい、という意図からです。
そうした要望の背景にはセラピスト自身の研鑽への思いがあるとも考えられますが、そもそも「陪席者ありき」の面接構造に依存しているとすれば、少し立ち止まって考えたいところでもあります。

本来、SV資料はセラピスト自身の記憶と記録によって作成されるべきものであり、陪席者に記録を全面的に委ねるのは、本質的には望ましい姿とは言えないように思います。
ただ、初学者としてはそのような状況に「それは違うのでは?」と声を上げづらいこともあるでしょう。
その場合は、無理のない範囲で協力しつつ、自分の学びが損なわれないよう意識を持ち続けることが大切なように思います。
事前に「何を学びたいか」を明確にする
陪席する前に、「この面接から何を学び取りたいのか?」を、できるかぎり具体的に意識しておくと、学びの質がぐっと高まります。
例えば:
- Thの介入のタイミング?
- Clの反応の変化?
- 沈黙の扱い方?
- 共感的な傾聴態度とは?
- 特定の技法がどのように使われるか?
- クライアントの抵抗への対応?
など、具体的な目標を持つことで、より能動的に面接を観察できます。
目的意識を持つことで、同じ面接を見ていても、得られる気づきが深くなります。
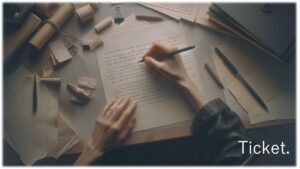
“いる”けれど、邪魔しない
陪席者として心がけたいのは、「場の流れを妨げない」こと。
例えば:
- 大きな音を立てて椅子を引く
- ため息を吐く
- メモ用紙をめくる音が大きい
- 突然離席して部屋を出る
などの行動は、Th-Cl間の繊細なやりとりに水を差すことがあります。
あくまで「そこにいるが、いないかのように」振る舞うことが理想です。
存在を消す必要はありませんが、場の流れにそっと寄り添うような所作を心がけてもらえると助かります。
初めての陪席で、どんな格好をしていけばよいのか、迷われている方もおられるかもしれませんね。服装に関する記事もありますので、あわせてご覧いただけたらと思います。
記録は、Clに見られてもいい内容で
面接中に記録をとる場合は、その内容が仮にクライエントさんの目に触れたとしても
差し支えないものであるかを常に意識しておきましょう。
主観的な解釈の記述は避け、あくまで客観的・簡潔なメモにとどめるのが望ましいです。
記録の仕方そのものが、心理士としての姿勢を映し出します。
倫理的な配慮を常に意識しましょう。
記録はあとからでもとることができます。
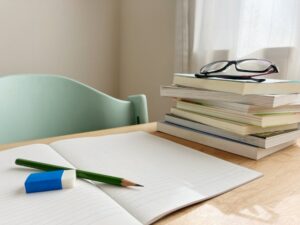
不安があるときは、事前にThに相談を
- 最初、どのように挨拶したらいいのか?
- どこに座ったらいいのか?
- どのような点で特に注意すべきか
- 記録の形式について
- 陪席後のフィードバックについて
など、少しでも不安や懸念がある場合は、必ず面接前に担当Thに相談をしましょう。
短時間でも事前に打ち合わせをすることで、安心して面接に臨むことができますし、Thにとってもあなたの意図がわかっていると進めやすくなります。
おわりに
初めての心理面接陪席は、座学では得られない貴重な経験となります。
陪席は「学びの場」であると同時に、「人間関係の場」でもあります。
ThとCl、そしてそこに加わるあなた。
三者の関係が、繊細に、丁寧に紡がれていくことを大切にしてほしいと願っています。
あなたの陪席が、豊かな臨床感覚を育てる第一歩となりますように、ぜひ実り多い学びの時間にしていただけたらと思います。
初めてケースに入る心理士さんへ──緊張との付き合い方
はじめてのクライエント対応、どうする?― 面接室へのご案内マナー —
面接中の沈黙をどう捉えるか?:心理士のための沈黙とのつきあい方







