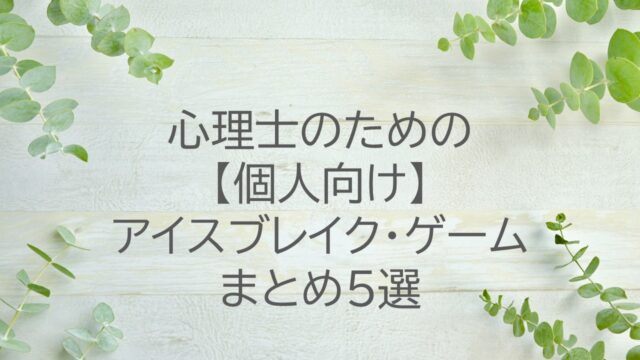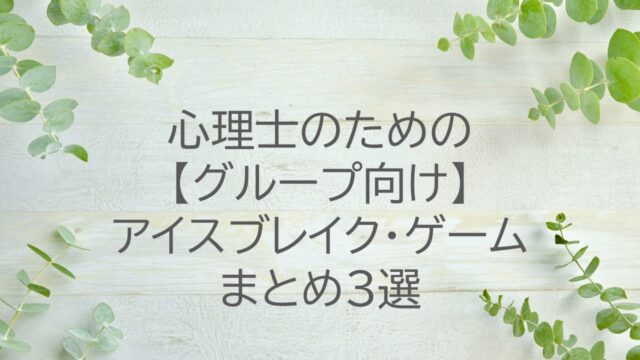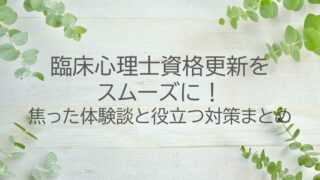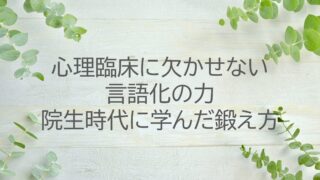心理士の仕事は面接だけじゃない!現場に欠かせない“名もなき仕事”とは?
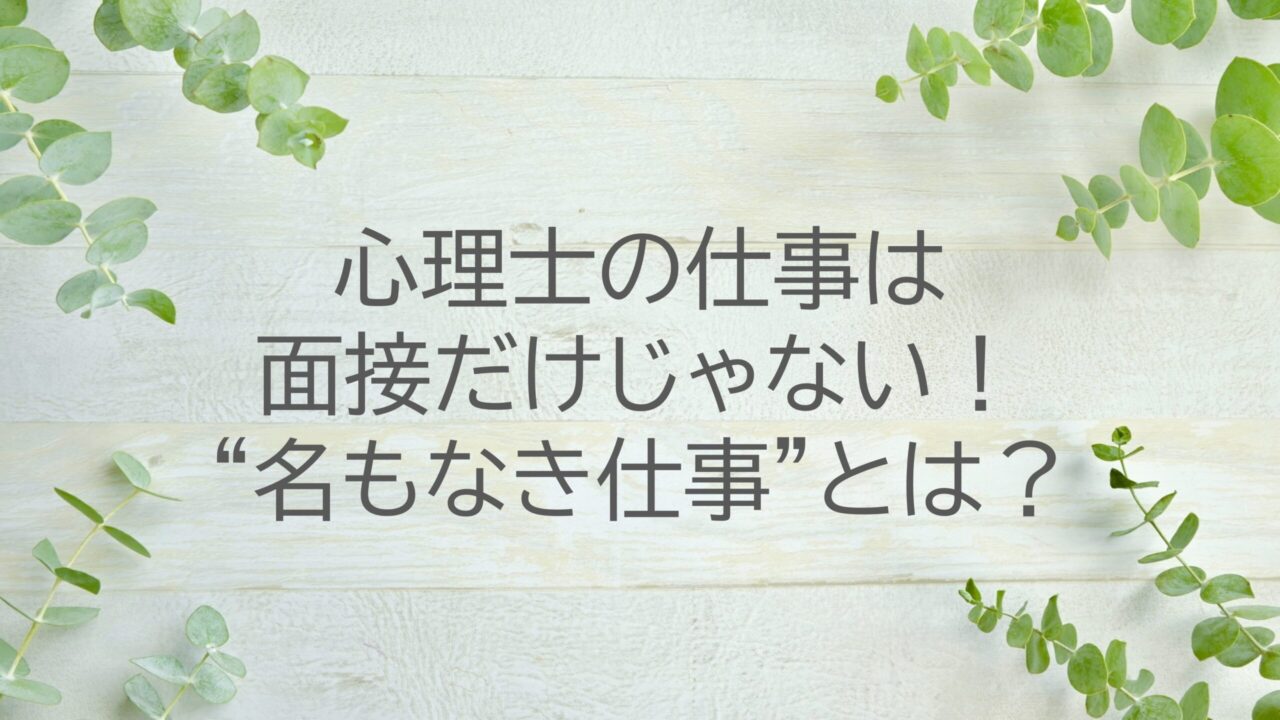
臨床心理士の仕事と聞いて、あなたはどんな姿を思い浮かべるでしょうか?
カウンセリング室でクライエントと向き合う姿、心理検査を分析する姿かもしれません。
しかし実際の現場では、そうした専門業務の陰に、誰も気に留めないような「名もなき仕事」が数多く存在します。
そして、それこそがクライエントの福祉を静かに支えています。

今回は、そんな「名もなき仕事」に焦点を当て、重要なその役割についてまとめてみたいと思います。
目を見て交わす挨拶が、職場の空気を作る

心理臨床の仕事は、一人で行うものではありません。
多職種連携が不可欠なチーム医療・チーム支援が基本です。
そのチームの中で、あなたは日頃からどれだけ同僚とコミュニケーションを取っていますか?
「おはようございます」「お疲れ様です」──そんな何気ない挨拶も、ただ言葉を発するだけでなく、相手の目をしっかり見て交わすだけで、その質は大きく変わります。
また、その挨拶から派生する一言二言の質の良い雑談が、さらに連携の足掛かりとして機能していきます。
体験談
私が以前、勤めていた職場での話です。
職場の空気が重く、朝の挨拶もほとんどの方が目を合わせない部署に配属されたことがありました。
その雰囲気に飲まれ、私もいつの間にか声を小さくするようになっていました。
そんな時、別の部署から異動してきた心理士さんが、毎朝変わらず元気に挨拶をしてくださったのです。
その方がいるだけで、場がパッと明るく和やかになるのを実感しました。
その方から「負けたらだめよ」「気にせず元気に挨拶!」と励まされ、それから私も意識してしっかり挨拶をするようにしました。
すると、同僚の表情や声のトーンから、その日の調子やちょっとした変化に気づけるようになっていきました。
クライエントの心の機微を察するように、同僚の些細な変化にも気づくこと。
そのために、挨拶は同僚との信頼関係を築く第一歩となり、チーム全体の雰囲気をより良いものにするための大切な基盤となります。
業務上の「手間」に気づき、改善する

あなたの職場には「ちょっとした手間だな」と感じる業務はありませんか?
同僚がふと立ち止まって何かを探している、いつも同じ作業で時間を取られている
――そんな場面を見かけることはないでしょうか。
みんなが「仕方ない」と思ってやり過ごしていることが、実は業務の効率を下げる要因になっていることがあります。
私たちは、自分自身の業務だけでなく、同僚がどのような導線で仕事をしているのか、
どのようなことに時間を費やしているのかを、意識的に観察することが大切です。
そして、その「手間」を解消するために、自分に何ができるかを考え、実行に移すことです。
体験談
新人だった頃、先輩心理士がキャビネットから検査用紙を探すのに苦労しているのを何度も目にしました。
ラベルが貼られていなかったからです。
私は空いている時間に、そのキャビネットにインデックスシールを貼ってみました。
すると、それに気づいた先輩心理士から「誰?これやったの!ありがとう!最高!」と、とても感謝されました。

心理士の仕事は一人で完結するものではなく、多職種との連携の中で進みます。
だからこそ、自分の業務導線だけでなく、同僚や他職種の導線にも目を向けることが大切だと、この一件で改めて感じました。
「名もなき仕事」は、クライエントの福祉に繋がる
これまでの話は、一見するとクライエントとは直接関係ないように思えるかもしれません。しかし、私は、職場の人間関係が円滑で、業務がスムーズに回ることは、結果的にクライエントの福祉に大きく貢献すると信じています。
たとえば、多忙な同僚が心理検査の準備に時間を取られることなく、本来の業務に集中できるようになれば、その分、クライエント一人ひとりに割ける時間が増えるかもしれません。
また、情報共有が密になれば、より質の高い支援を提供できるようになります。
そして、こうした働きやすい環境を整えるプロセス自体が、臨床心理士の専門性を物語っています。
たとえば、スタッフ間の連携を強化するために、スタッフルームにミーティング用のデスクとチェアを配置したいと考えたとしましょう。
その際、誰に相談し、誰の協力を得て、どのような手順を踏むのが最善かを、組織の力動的な見立てを立てながら検討します。
そのうえで、まずは誰に何を依頼するのかを組み立て、後方での「根回し」を行う。
この環境が整えられれば、連携のための話し合いの機会が増え、結果的にクライエントの福祉に繋がる───そうした「根回し」の積み重ねこそが、クライエントの福祉に繋がる確かな土台となっていきます。
臨床心理士は職場の「潤滑油」でありたい

私は、臨床心理士は職場の潤滑油でありたいと常々考えています。
臨床心理士の仕事は、面接室内でのことに限りません。
潤滑油が機械の摩擦を減らし、動きを滑らかにするように、私たちは職場の人間関係の摩擦を減らし、チーム全体の協働を円滑に進めるように配置された存在でもあります。
この「潤滑油」として機能するためには、日頃から同僚との関係性の土壌を耕すこと、つまり「根回し」が肝になってくるのです。
まとめ:臨床心理士≒臨床根回士?
 今回紹介した心理士の「名もなき仕事」は、評価表や業務記録に残ることはほとんどありません。しかし、それがあるからこそ現場が回り、心理士が本来の力を発揮できるのだと思います。
今回紹介した心理士の「名もなき仕事」は、評価表や業務記録に残ることはほとんどありません。しかし、それがあるからこそ現場が回り、心理士が本来の力を発揮できるのだと思います。
だから私は、冗談半分、本気半分で「臨床心理士と書いて臨床根回士(ねまわし)」と読んでもいいのでは、と言いたくなるのです。
この「名もなき仕事」に誇りを持ち、日々の業務に励むことが、きっと私たちの専門職としての幅を広げ、これからの心理臨床現場を支える大事な視点になるとも思っています。
今回紹介したのは「名もなき仕事」のほんの一部です。
みなさんの思う、心理士の「名もなき仕事」にはどんなものがありますか?