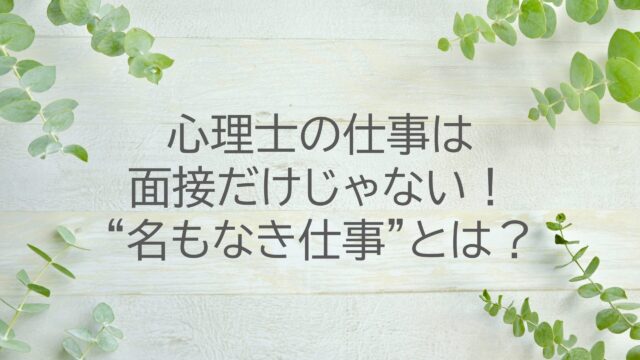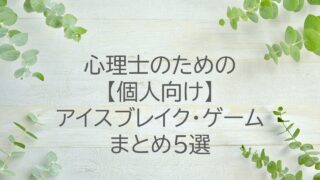【公認心理師1年生】新社会人のための入職準備ガイド

こんにちは。私たちは心理臨床コミュニティTicekt.を運営している臨床心理士・公認心理師です。
公認心理師養成大学院、臨床心理士養成指定大学院のM2の皆さん、修了おめでとうございます。
修士課程の2年間は、本当にあっという間に過ぎたのではないでしょうか。
特にM2では、就活と並行して国家試験の勉強、修論、臨床実習など、数々のイベントを乗り越え国試受験までたどり着いたことと思います。
修了の喜びも束の間、3月末には国家試験の合格発表があり、4月から新社会人としての生活がスタートする方も多いことでしょう。
入職予定の臨床領域によって、準備すべきことは多少異なるかもしれませんが、基本は共通することが多いと思います。

この記事では、新社会人として臨床現場に飛び込む前に、準備しておきたい3つの視点をご紹介していきたいと思います。
業務概要の再確認
まずはこれから始めましょう。
入職先の職場によっては、3月中に研修がある場合もあります。
4月以降の仕事スタイルができるだけ具体的にイメージできるよう、業務概要について事前に調べておくと良いでしょう。
欠員募集での採用の場合は、前任者からの引継ぎがあるかもしれません。
その場合
入職予定の職場が統計資料を公開している場合は、それもチェックしましょう。
そうすることで一人当たりの年間担当ケース数や月間担当ケース数のおおよそのイメージがつきやすくなります。
統計資料の中に心理検査の実施件数や種別が公開されている場合は、入職後、その検査を担当する可能性が高いと考えられます。
そのため、関連する心理検査の練習や準備をしておくと良いでしょう。
症例種別が公開されている場合は、その機関が身体疾患の患者さん、うつ・不安の患者さん、または、発達障害診療をメインとしているかなど、専門領域の傾向が見えてきます。
つまり
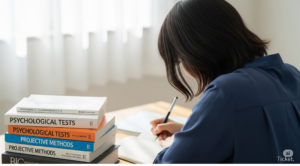
心理検査の復習
心理検査、特に知能検査を使う職場は多いのではないでしょうか。
入職予定の領域によって、よく使用する心理検査の種別は様々だと思いますが、知能検査を基本として、使用する可能性の高い心理検査の復習をしておくと良いと思います。
在籍校で心理検査の貸し出しをしてもらえる場合は、以下のことをお勧めします。
引っ越しに最適な場所
在学中は大学の近くに住んでいた方も多いでしょう。
就職先によっては、引っ越しが必要になる方もおられると思います。
職場と自宅の距離、つまり通勤距離について、どのくらいが最適なのかは、人によって様々かもしれません。
- できるだけ通勤時間は短く、退勤後の時間を充実させたい、という方
- ある程度距離があった方が、プライベートと仕事のオンオフを切り替えやすい方
いずれにしても、お勧めしたいのは
生活圏が重なると、プライベートな場面で患者さんやクライエントさんと遭遇する確率が高くなります。
そのことを全く気にされない心理士さんもおられるかもしれません。
でも、クライエントさんの心情も考慮すると、どうでしょうか。
と私は考えています。

個人の経験に基づく準備のすすめ
私は修了後すぐに、子どもを対象とした機関への就職が決まっていましたので、在学中にWISCと田中ビネー知能検査の復習を重点的に行いました。
また、入職予定先の公開統計資料も調べ、年間どのくらいの子どもたちに関わることになるのか、具体的なイメージを膨らませました。
さらに、徹底的に行ったのは
先輩心理士さんがいらっしゃるような職場であれば、入職後に丁寧なOJTが受けられることもあります。
しかし、より早く、現場で活躍できる心理士になるには、指示されるのを待つだけでなく、上記のような事前準備をしておくことをお勧めします。
以上、入職前の準備として、大きく3つのことをご紹介しました。
- 業務概要の再確認
- 心理検査の復習
- 居住地の検討
入職時期まで残りわずかですが、心理士1年生として新社会人になる読者のみなさんのお役に立てれば幸いです。