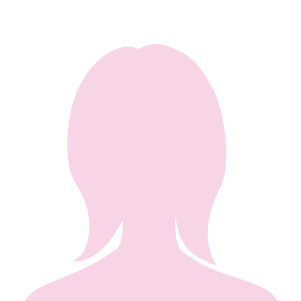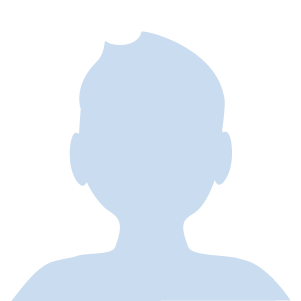知能検査の結果に「偏差IQ」と「比例IQ」という2種類の表記があることをご存じですか?
この違いを知っておくことで、保護者や関係者からの質問に適切に対応でき、より的確なフィードバックにつながります。
この記事では、心理検査でよく用いられる「ウェクスラー式(偏差IQ)」と「ビネー式(比例IQ)」の違いについて、具体例を用いながらわかりやすく解説します。
IQ:よくある質問
時折、検査を受けられた保護者の方から
といった質問を受けること、ありませんか?
普段、知能検査を実施している方であれば、こうした質問はよくあるものだと思います。
心理臨床初学者の皆さんの中には、このような質問に戸惑ってしまったという方も少なくないのではないでしょうか。
今回の記事はこうした質問にもスムーズに対応できるようになるヒントが含まれているかと思います。
タイトルにある通り
IQには偏差IQと比例IQの2種類があることはご存知でしょうか。

偏差IQと比例IQは、どちらも知能検査の結果を表す指標ですが、その算出方法と意味合いに大きな違いがあります。
このことをよく理解しておくと、前述の保護者の方の質問にもスムーズに対応することができるでしょう。
偏差IQ:ウェクスラー式
偏差IQとは
同じ年齢の集団の中でどの程度の位置にあるか
を表した数値のことです。
つまり、その方の
同年齢の集団内での位置
を表しています。
比例IQ:ビネー式
比例IQとは
何歳程度の発達ができているか
を表した数値のことです。
つまり、その方の
生活年齢に対する精神年齢の比率
を表しています。
偏差IQと比例IQの違い
両者の違いをまとめると以下のようになります。
| 比例IQ | 偏差IQ | |
| 意味合い | 基準生活年齢に対する精神年齢の比率 | 同年齢集団内での相対的な位置 |
| 算出方法 | (精神年齢 ÷ 生活年齢) × 100 | 同年齢集団の平均を100とし、標準偏差で位置を算出 |
| 適用年齢 | 主に子ども | 全ての年齢層 |
このように、偏差IQと比例IQでは、数値の算出方法も異なりますし、数値の表す意味も異なります。
どっちの数値が正しいの?の答え
では、冒頭での保護者の方からのよくある質問
に立ち返ってみましょう。
結論としては、
というのが答えです。
これは、異なる物差しで測った数値を比較するようなものです。それぞれが異なる側面を捉えているため、どちらか一方が「正しい」というものではないのです。
例を用いて考えてみよう
例えば、10歳のAさんが、
WISCとビネーの両検査を受検し、
両検査ともIQが「80」だったとします。
*実際にはビネーの方が10~20程度、数値が高く出やすいと言われていますが、今回は同数値と仮定して考えてみます。

10歳の集団の中に属した時、Aさんは平均の下の位置
Aさんの精神年齢は10歳を100%とした時、80%の発達
=(だいたい8歳ぐらいの発達段階)
このように、同じ「80」という数値でもそれぞれのIQが表す意味が異なるため、単純に比較することが難しいのです。
前述の保護者の方の「ビネーの方が10以上高い数値だった」というようなことをおっしゃられた時には、以下のように解説できるのではないでしょうか。
この解説に加え、
その方のWISCの各主要指標得点や下位検査の評価点まで目を向けると、精神年齢だけでは捉えられなかった、その方の生活を難しくさせている要因がどこにあるのかのヒントも見えてきます。
まとめ
今回は、偏差IQと比例IQについてまとめて解説してきました。
それぞれの特徴を理解した上で、検査結果のフィードバックが行えるようになると、その方の理解もより深まるのではないでしょうか。
フィードバック面接においては、
数値の意味を理解した上で、日常起こりうる事象やエピソードとのすり合わせを行い、一緒に対策を練ることができると、よりその方の日常生活に活きる検査結果になるのではないかと思います。
偏差IQにしても比例IQにしても、
その方の一側面を捉えるためのヒントにしかなりません。
日常生活の様子を丁寧に拾い上げながら、検査の結果とすり合わせ、より整合性のある所見作成・フィードバックができるようになりたいですね。
-
数値の意味を丁寧に説明する
-
生活場面や具体的なエピソードと結びつける
-
数字以外の側面も総合的に評価する