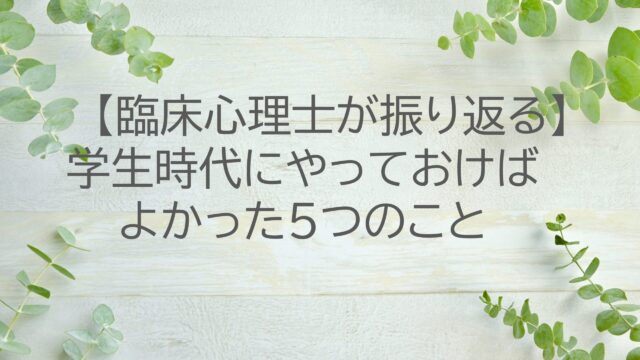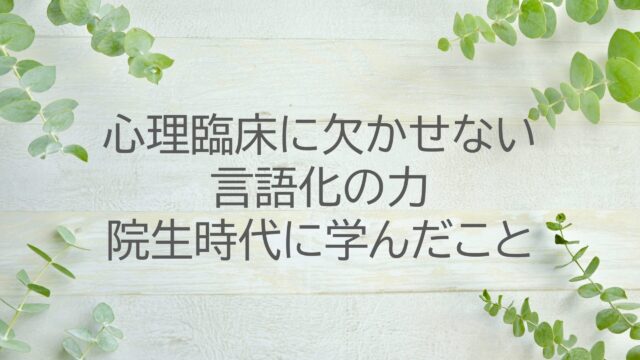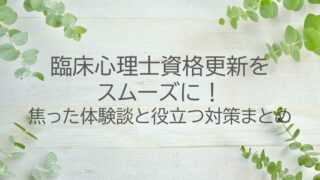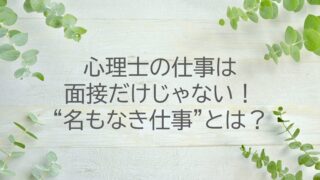若手心理士のためのグループワーク企画実践例|依頼から実施・反省までのプロセス紹介
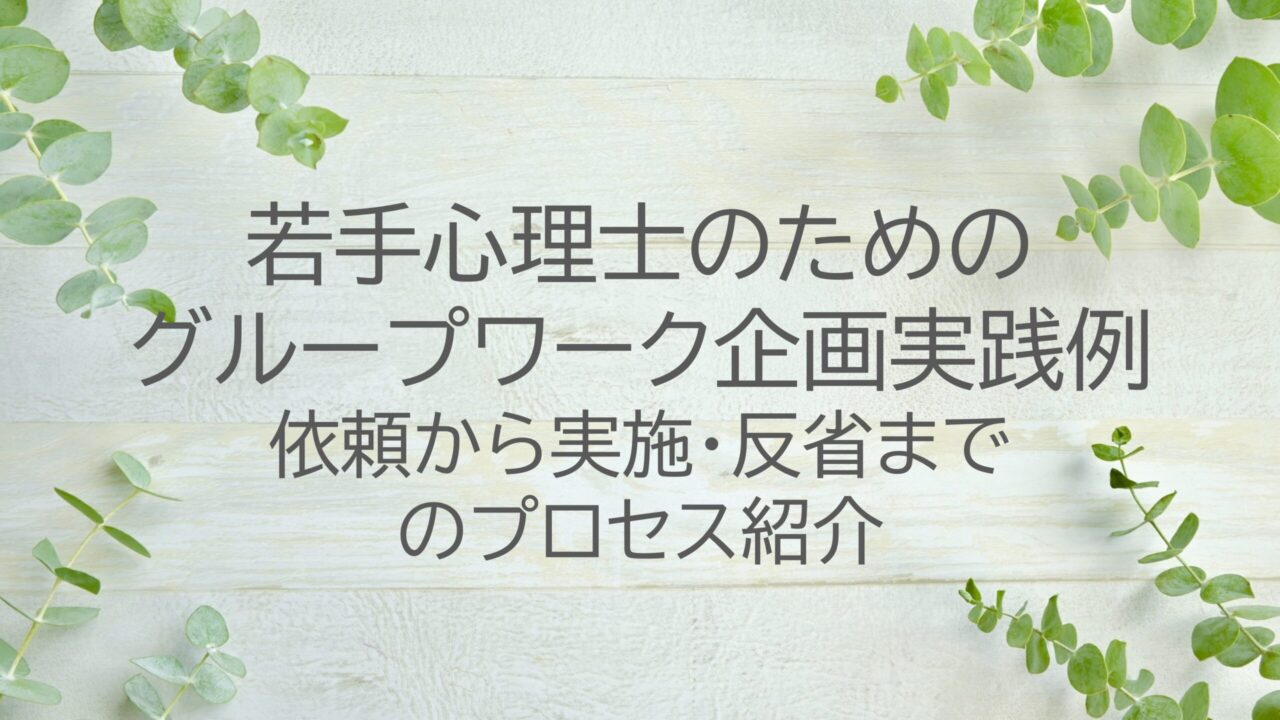
※本記事にはプロモーションが含まれています。
初めてグループワークを任された時、「どこからどう手をつけたら良いのかわからない」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
以前の記事【若手心理士向け】初めてグループワークを任されたときに考えるべき5つの視点では、企画を進める際に押さえておきたいポイントをご紹介しました。
しかし、「5つの視点は分かったけれど、実際にどのように形にしていけばいいの?」と思われた方もいるかもしれません。
この記事では、私が実際に5つの視点を活用した、あるグループワークの具体的なプロセスを、依頼から実施、そして反省まで、ご紹介します。
企画はどこから始まるのか? ― ご依頼までの経緯
私がグループワークの企画を任されたのは、学生時代からボランティアで関わっていた学校でした。
数年間お世話になっていたご縁があり、私の専門性や人柄を知ってくださっていた管理職の先生が、「ぜひお願いしたい」と声をかけてくださったのです。

この経験から、日頃から良好な人間関係を築いておくことの大切さを改めて実感しました。信頼関係があるからこそ、依頼という形で仕事につながるのだと気づかされました。
企画の舞台:人間性を育む学校
企画にあたり、まず私が着目したのは、依頼元の学校の風土です。
私が依頼を受けたその学校は、生徒の人間性を育むことを重視していました。
この校風を考慮し、単純に知識やスキルを習得するようなワークよりも、自己理解・他者理解が促され、社会で生き抜くための柔軟性や協調性を体験できるようなワークが適切だと考えました。

参加者の特徴:150名の研修
次に、参加者の特徴を分析しました。
今回の参加者は150名程度。
実施時期は入学から1ヶ月が経った頃の研修です。
まだお互いを深く知らない「顔見知り」程度の関係性を考慮し、最初から深い自己開示を求めるワークは避けることにしました。
そこで望ましいと考えたのは、全員が積極的に参加しなくても成り立ち、誰かがそこにいるだけでも大丈夫なワークです。
協調的な関わりを促しつつ、参加者一人ひとりの心理的な安全性を確保できる内容を目指しました。

グループワークの位置づけ
組織の風土、参加者の特徴が整理されたら、次は今回のグループワークの位置づけを明確にしていきます。
今回のワークは単回のセッションで、研修の目的は「仲間づくりと粘り強さの育成」でした。ワーク後も同じ集団での学校生活が続いていきます。
この点を踏まえ、以下の3点をワークの目標に据えました。
- ワークを通じてクラスメイトを少しでも知ること
- 「この集団、悪くないかも」と思える体験をつくること
- 担任の先生との関わりも自然に生まれるようにすること
また、いきなり大人数で取り組むより、「少人数→全体」へと段階的に広がる設計にすることで、集団への抵抗感を和らげる工夫を盛り込みました。
時間枠は1時間
ある程度ワークの方向性が見えてきたら、次は、時間枠にどうその体験を収めるかを考えなければなりません。
今回のこのグループに与えられた時間は1時間で、説明とクロージングをあわせて10分と想定すると、実質のワーク時間は50分間です。
この時間枠を考慮して以下の2点の構想を得ました。
- 集中力を考えると、単一のワークより3段階程度の仕掛けが必要
- 生徒たちが単調に感じないように、場所を移動するウォークラリー形式や脱出ゲームのようなものが良い
会場の物理的条件を確認する

企画が固まってきたら、次は会場の物理的な条件を実際に見て確認します。
管理職の先生に許可をいただき、研修会場を直接下見させていただきました。
使える部屋や備品、間仕切りが可能かなど、細かく親身に教えていただけました。
下見の結果、複数の部屋が使用可能で、開始と終了は大ホールが使えること、そして間仕切りが柔軟にできることが分かり、「クラス対抗の脱出ゲーム形式」で進めることに決定しました。
計画通りにいかないのも臨床。反省点。
企画したワークは順調に進み、ほとんどのグループが45分ほどでゴールにたどり着きました。
しかし、ここで問題が発生します。
ゴールした生徒たちが手持ち無沙汰になり、待ち時間が生まれてしまったのです。
このままでは場がダレてあまり良くないよな…と感じた瞬間、生徒間での小さなトラブルが発生しました。
「あと一歩早く、クロージングに移っていれば…」と後悔が残りました。
この経験から得た教訓は、グループワークでは時間の余りが不安やトラブルの温床になりがちだということです。特にエネルギーのある思春期・青年期を対象とする場合、余裕を持たせすぎない時間設計が重要という学びを得ました。
クロージングで何を伝えたか

今回のワークでは、あえてトラブルにも触れてクロージングをしました。
全員が目撃していたのに、このことに触れずに終わるのは違うと感じたからです。
まず、今回のワークの目的が、お互いのことを知り、関わることへの緊張感を和らげることだったと伝えました。
その上で、以下の4点を生徒たちに率直に伝え、ワークを締めくくりました。
- 人との衝突も、コミュニケーションとしての一つの方法であること。
- 人と関わるうえで腹が立つことは誰にでもあること。
- ただ、その伝え方には工夫のし甲斐があること。
- これからの学校生活の中で、お互いが心地よくすごせるコミュニケーションのあり方とは何か、発見していく時間にしてほしいこと。
まとめ
今回ご紹介したのは、私が若手の頃に担当させていただいたグループワークの実践例です。
完璧な成功ではありませんでしたが、参加者の様子や実施後の反省点から多くの学びを得ることができました。
計画通りにいかないこともありますが、その反省が次の実践に生きてきます。
特に、「事前にどれだけ周到に準備しても、現場では予期せぬことが起こりうる」という臨床の現実を改めて思い知らされました。
また、企画に際しては「日常的な関係づくりの大切さ」と、対象者の特徴によっては「余白時間への配慮」の重要性を改めて実感する機会となりました。
今回ご紹介した実践例が、これからグループワークを企画する若手心理士の皆さんの参考になれば幸いです。