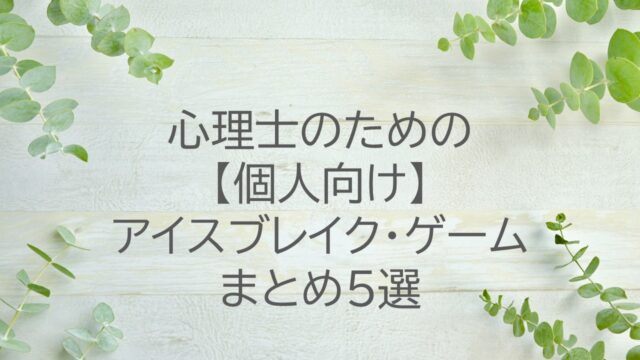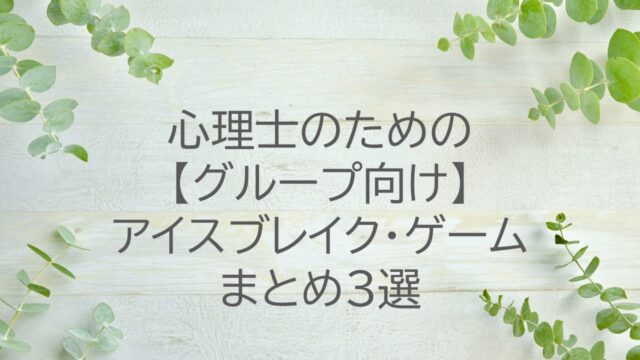【若手心理士向け】初めてグループワークを任されたときに考えるべき5つの視点

心理士として働いていると、ある日突然「グループワークをお願いできますか?」と依頼されることがあります。
特に、数年の臨床経験を積んだ頃には信頼の証として、こうした機会が増えてきます。
しかし、
「個別面接には馴染みがあるけれど、グループって何から考えればいいの?」という戸惑いを抱く方も多いのではないでしょうか。
参加者にとって実りある時間を作るためには、事前の情報収集が何よりも重要です。
グループワークの成功は、センスや経験だけで決まるものではありません。

この記事では、初めてグループワークの企画を任された心理士さんが、どこからどう手をつけていけばいいのかを整理するための視点をご紹介します。
本記事は、グループワークの具体的な方法や介入技法を解説するものではなく、
企画を検討する際に「どんな情報を整理しておくと考えやすいか」という視点をまとめたものです。
ポイントは、「すぐにワーク内容を決めようとしないこと」です。
まずは、これからご紹介する5つの情報を丁寧に集めることから始めましょう。
グループワーク企画でまず押さえるべき5つの視点
企画をスタートさせる前に、いきなり「どんなワークをするか」を考えるのではなく、以下の5つの情報を丁寧に整理していくことが、成功への近道です。
ステップ1. 依頼された組織の成り立ち・風土・性質を知る
グループワークの企画は、その「土壌」を知らずには始まりません。
依頼元が学校なのか、福祉施設なのか、企業なのかによって目的も求められるものも大きく異なります。
例えば:
- 企業なら…「成果主義」なのか「協調性」を重んじるのか
- 学校なら…「自由な校風」なのか「規律を重んじる」のか
- 福祉施設なら…支援対象の特性や関係性の構造に着目する
こうしたその組織ならではの文化や特性を理解することは非常に大切です。
この背景を知ることで、ワークの目的設定や内容、進行のトーンまで、組織にフィットしたものを検討できます。
同じ「コミュニケーションを促進したい」というテーマでも、その背景にある文化や歴史、言葉遣いの違い、権力構造によってアプローチは変わってきます。
まずは、その組織が
- どんな理念や価値観を持っているのか
- どのような雰囲気や人間関係の特徴があるのか
に目を向けてみましょう。

ステップ2.グループワーク参加者の特徴を知る
参加者が「誰で、何名で、どんなニーズや課題を抱えているのか」を知ることも非常に重要です。
年齢層、職種、立場、関係性の深さ、対人スキルのばらつき、グループワークへの経験値などを把握することで、どのくらいの開示が可能か、どこまで踏み込めるかの見立てが立ってきます。
もし、参加者の多様性が高いのであれば、誰もが安心して参加できるような細やかな配慮が必要です。
例えば、初対面の人ばかりであれば、アイスブレイクに時間をかけ、お互いの共通点を見つけられるようなワークから始めるのが良いでしょう。
また、特定の課題を抱えている参加者がいる場合は、その課題に寄り添った内容にすることも重要です。
対象理解なくして、効果的なグループ構成や進行は難しいものです。

ステップ3.グループワークの「位置づけ」を知る
そのワークは、組織の中でどういう意味を持っているのでしょうか?
- 単発のイベントなのか、継続的な取り組みの一部なのか。
- 研修の一環として位置づけられているのか。
- 心理的ケアを目的としたものであるのか。
例えば、新入社員研修や新入学生の宿泊研修の一環等であれば、自己紹介やチームビルディングに重点を置いたワークが効果的です。
一方で、
既知集団での課題解決や関係性の変容等が目的であれば、具体的な問題提起と解決策の検討を促すワークや新たな一面が知れるようなワークが求められるでしょう。
- このワークが終わったとき、どんな状態を目指すのか
- 参加者にどんな体験をしてほしいのか
を整理することが、内容設計の出発点になります。
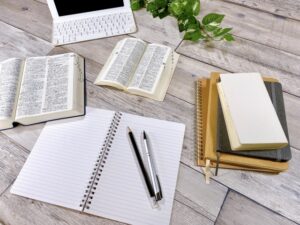
ステップ4.グループワークの時間枠を知る
与えられた時間は、どれくらいでしょうか?
30分なのか、半日なのか、それとも数日間にわたるものなのかによって、組めるワークの内容は大きく変わってきます。
時間の長さは、できることの範囲を決める大事な情報です。
90分あればできることも、30分では大きく制限されますし、逆に長すぎても集中が続かないこともあります。
短い時間であれば、簡潔でポイントが明確なワークを選び、効率的な進行を心がける必要があります。
逆に時間に余裕がある場合は、深い対話や体験を促すワークを取り入れ、参加者の学び・体験を最大化することもできます。
時間に合わせた「目的」と「構造」の調整が、満足度の高いワークにつながります。

ステップ5.会場の物理的条件を把握する
意外と見落としがちなのが、会場の物理的な条件です。
椅子の並びは固定なのか、円になれるのか。
広さや音の反響、空調、ホワイトボードやプロジェクターの有無、外からの視線なども、安心して話せる空間づくりに大きく関わってきます。
たとえば:
- ディスカッション中心のワーク:参加者全員が顔を見合わせられるような配置が理想的。
- 身体を動かすワーク:十分なスペースが必要です。
会場の物理的な制約を理解することで、ワークの選択肢を絞り込み、より実践的な計画を立てることができます。
可能ならば事前に会場の下見をしたり、会場スタッフとの打ち合わせをしておくと安心です。

情報がそろって、初めて「最適なワーク」が見えてくる
よくある誤解は、「どんなワークがいいかをまず考える」こと。
でも実際は、ここまでご紹介した5つの情報が揃って初めて、「何がその場にふさわしいか」が見えてきます。
-
誰のために
-
何を目的として
-
どんな時間・空間の中で
-
どのような体験を届けるか
この全体像が整理されたとき、初めて“意味ある構成”が生まれます。
まとめ:ワーク設計に「正解」はない。でも「手がかり」はある
グループワークの企画・構成の立て方には、絶対的な「正解」はありません。
その場その時、その人たちの関係性や空気感によって、同じワークでも全く違う意味を持ちます。
だからこそ、丁寧に観察し、耳を傾け、柔軟に組み立てていく姿勢が大切です。
見立て方は個別面接でもグループでも、大きくは変わらないとも思っています。
個人も組織も一つの”システム”として見立てていくこと。
その視点を持つことで、ワークは一過性の「イベント」ではなく、変化の“きっかけ”になるはずです。
あなたの関わりが、参加者の方々の「ちょっとした変化」のきっかけとなりますように。