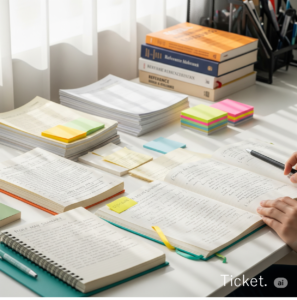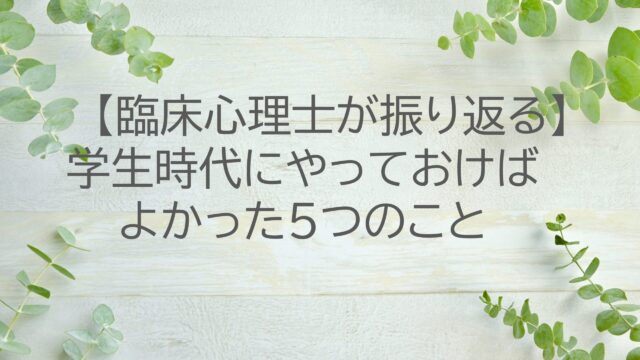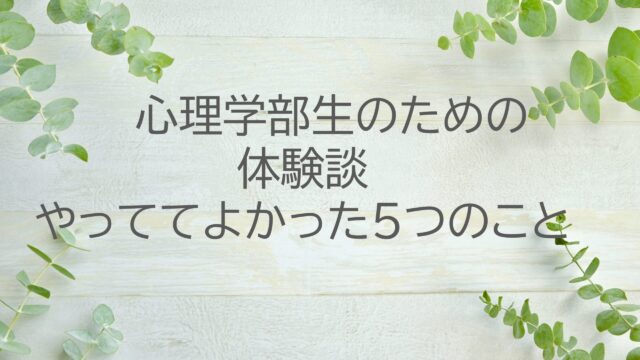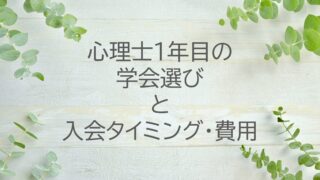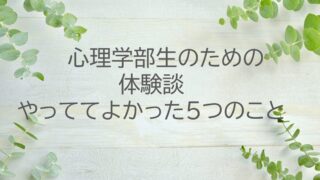大学院入試、いつからどうやって勉強した?私のスケジュールと工夫を紹介します
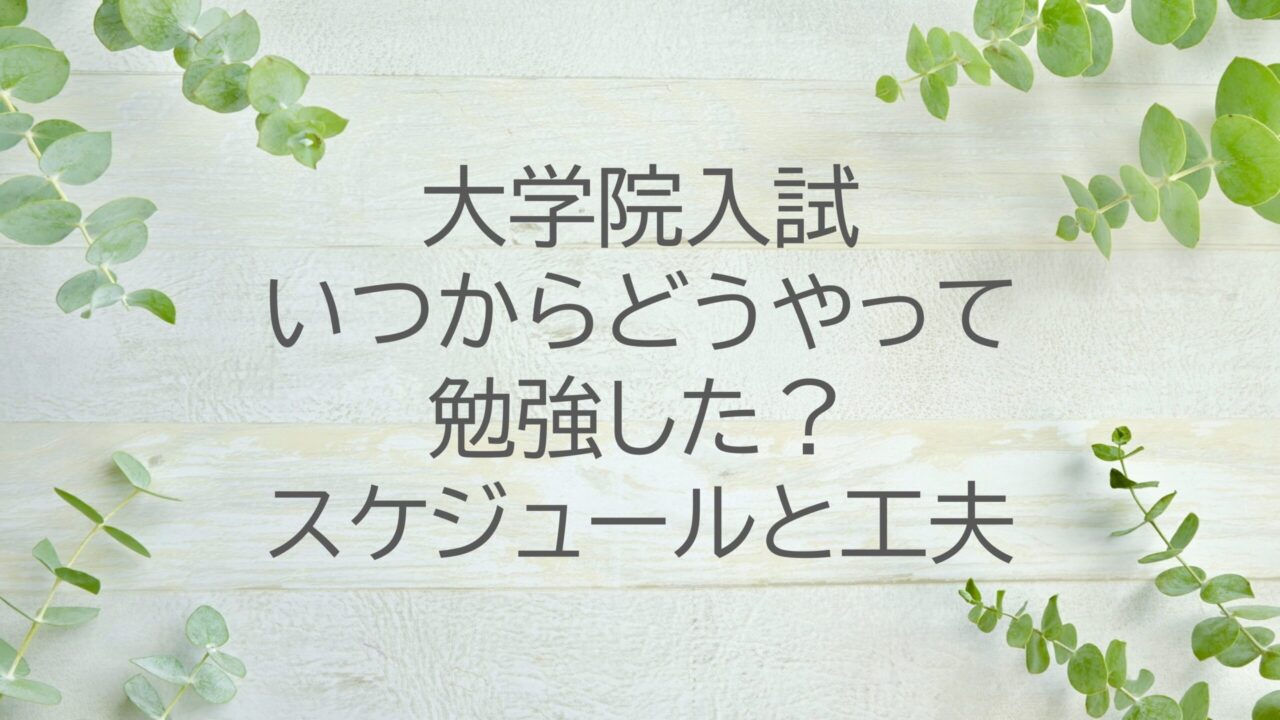
「大学院進学を考えているけど、勉強っていつから始めればいいの?」
「院試ってどんな対策をすればいいのか分からない…」
そんな悩みを持つ方に向けて、今回は私が実際に行った大学院入試対策のスケジュールと勉強法をご紹介します。心理系大学院を目指す方にとって、少しでも参考になれば嬉しいです。
※本記事は、筆者個人の経験をもとにした体験談であり、特定の合格方法や成果を保証するものではありません。

勉強スタートは大学3年生の夏から
私の大学院入試対策は、大学3年生の夏にスタートしました。部活動やアルバイトと並行して、まずは毎日1時間、勉強を「習慣化」することを目標にしました。いきなり長時間ではなく、無理なく続けることを大切にしたのです。
自分だけの「オリジナルノート」作り
-
1科目につき、ノート1冊にまとめる
-
専門用語は、提唱者の名前と英語表記も併記
-
よく出てくる単語は、ノートに正の字で出現回数を記録
-
足りない知識は、『心理臨床大辞典』や『ヒルガードの心理学』で補強
各ポイントの具体例:
①1科目につき、ノート1冊にまとめる
・複数冊にまたがらず、1冊におさめるのがポイント。
・どのノートのどのあたりにあるか場所で記憶もしやすくなる。
②専門用語は、提唱者の名前と英語表記も併記
・英文の読解問題が出題されることが多いため、あわせて覚える。
③よく出てくる単語は、ノートに正の字で出現回数を記録
・どの用語が重要であるか、視覚的に把握。
④足りない知識は、『心理臨床大辞典』や『ヒルガードの心理学』で補強
・臨床心理学系の知識は「心理臨床大辞典」で。
・基礎心理学系の知識は「ヒルガードの心理学」で。
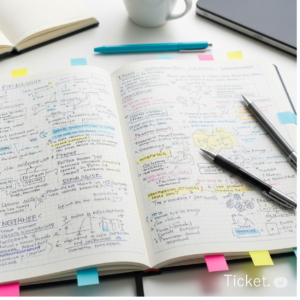
このように、自分でまとめ直すことで、知識が定着するだけでなく、のちのちの復習にも役立つ「自分だけのオリジナル参考書」になりました。
自分が理解しやすい言葉でまとめられ、必要な情報がすべて詰まったこのノートは、後々の学習においてかけがえのない財産となりました。
過去問演習は大学4年の春から
大学3年の3月までに基礎固めを終え、大学4年の春からは過去問にシフト。
複数の志望校の過去問を3〜5年分取り寄せ、以下のように取り組みました。
- 論述形式での解答練習
- 頻出テーマの把握
- 最新情報の追加
各ポイントの具体例:
①論述形式での解答練習
・実際の試験を想定して。
・知識を覚えるだけでなく、それを論理的に構成し、
説得力のある文章で表現する練習。
②頻出テーマの把握
・出題された専門用語やテーマについては、
作成した各ノートに「正」の字を追記。
・頻出問題を視覚的に把握し、対策を立てる。
・3~5年分解くことでその大学院の傾向も把握できる。
③最新情報の追加
・新しく学んだ知識や、過去問で出てきた知らない概念は、
作成したノートに付箋を貼ってどんどん補填。
・情報を育てていく感覚。
このステップで、頻出テーマや苦手分野が明確になり、効率よく対策できるようになりました。
この時期は、1日3~10時間と、確保できる最大限の時間を勉強に充てました。
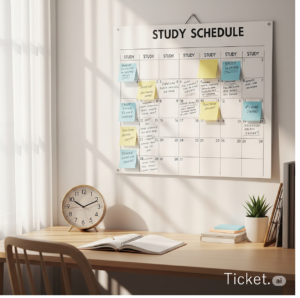
勉強時間の目安
勉強時間は以下のように段階的に増やしていきました。
| 時期 | 1日の勉強時間(目安) |
|---|---|
| 大学3年 夏〜冬 | 1時間(習慣づけ重視) |
| 冬〜春 | 3〜6時間 |
| 大学4年 春以降 | 3〜10時間(毎日継続) |
この勉強法はその後も役立った
このとき作ったノートは、臨床心理士試験や公認心理師試験の際にも活躍しました。
自分の理解度に合わせたまとめ方をしていたので、後から見返しても非常に分かりやすく、長期的な学びの土台になったと思います。
まとめ|「自分だけの参考書」を育てよう
大学院入試は、単なる暗記ではなく、理解と表現力が求められます。
そのためにも、早い段階から自分のペースで取り組み、自分なりの学習ツールを作っていくことが重要です。
大学院入試は決して楽な道のりではありませんが、計画的に、そして効率的に学習を進めることで、合格への近道になるはずです。
この体験談が、これから大学院を目指す皆さんの参考になれば幸いです。