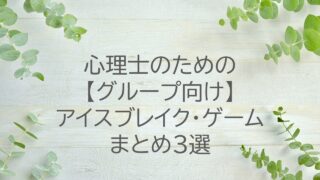研修や集団療法に使える!心理士のための個人向けアイスブレイクゲーム5選
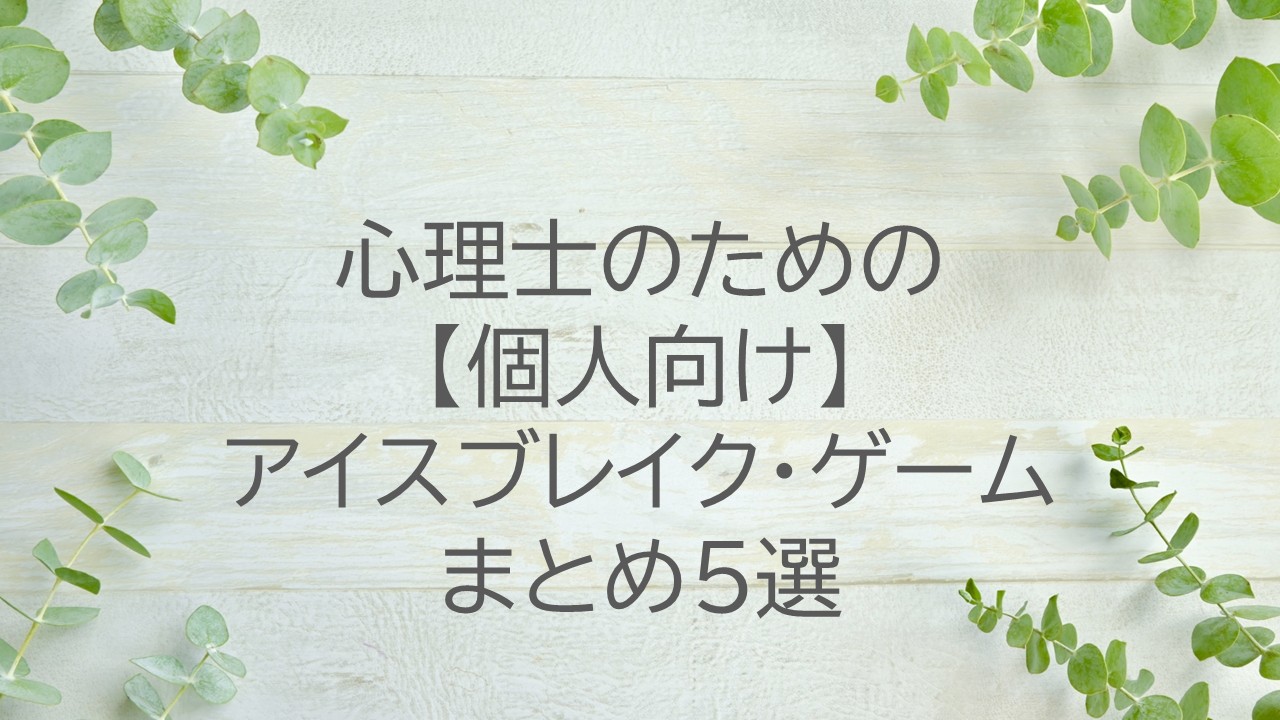
新年度が始まり、講義や集団療法、研修を担当することになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
資料作りや構成を練ることに時間をかける一方で、
「場の空気をいかに居心地よくするか」という視点は、つい後回しになってしまうこともあります。
そんなときに役立つのが、アイスブレイク。
参加者も担当者も、少し気持ちがほぐれることで、その後の流れがスムーズになることが多いです。
この記事では、参加者が“1人で取り組める”アイスブレイク・ゲームを5選と、心理士として使ってみた感想をご紹介します。
研修で30人以上の参加者がいるような場面でも、グループを作ったり会話をしたりせず、個人で完結できるゲームばかりなので、話すことに不安がある方が多い場面でも安心して取り入れられます。いくつか知っておくだけで、急な進行にも柔軟に対応できます。ぜひ実際の場面で使ってみてください。
※研修や集団療法で使用する際は、参加者の特性や場の目的に配慮し、無理のない範囲で取り入れてください。
アイスブレイクとは?
アイスブレイクとは、「氷を溶かす」ように場の緊張をほぐすためのエクササイズのことです。ほかにも「ウォーミングアップ」と呼ばれることもあります。ビジネスシーンでは、「雑談」がアイスブレイクと捉えられることも多いですね。
この記事では、研修・講義・集団療法などの場で、アイスブレイクを目的として行うゲームを紹介します。
アイスブレイクを取り入れるメリット
1. 緊張をほぐす
研修の冒頭にアイスブレイクを行うことで、研修担当者も参加者もリラックスできます。参加者の笑顔や笑い声がその場の空気を大きく変えてくれるはずです。
2. 眠気対策
午後の研修では、参加者が眠くなることも。アイスブレイクのゲームを取り入れると、一気に空気がリフレッシュされ、眠気も吹き飛びます。
3. 相互理解を深める
(グループワークの場合)相手がどんな人か、どんな考え方を持っているかを知ることができます。
4. コミュニケーションの促進
(グループワークの場合)参加者同士が協力して行うゲームは、コミュニケーションを促進し、チームワークを高める効果があります。
どんなアイスブレイクを選ぶか?

アイスブレイクとひとくちに言っても、内容やスタイルはさまざまです。
場を一気に盛り上げるものもあれば、手を動かしたり、頭を使ったりしながら1人で取り組めるシンプルなものもあります。
大切なのは、研修や講義の目的、参加者の特性、場の雰囲気に合わせて無理のないものを選ぶことです。
たとえば、研修の初回や、参加者同士がまだ初対面のような場面では、いきなりグループで話し合ったり、相互理解を深めるようなゲームを行うと、緊張を強めてしまうこともあります。
そんなときは、1人で完結できるアイスブレイクを取り入れるのがおすすめです。
隣の人と話したり、グループを作ったりしなくてもいいので、どんな人でも取り組みやすく、安心感のある雰囲気を作りやすくなります。
特に、大人数の研修や、年齢や立場の異なる人が混在する場面では、まずは全員が同じペースで参加できる簡単なゲームから始めることで、自然に空気がゆるみ、その後の学びや対話にもつながりやすくなります。
アイスブレイク・ゲーム5選(個人編)
ここでは、グループを作らずに、参加者が椅子に座った状態で1人でできるアイスブレイク・ゲームを5つ紹介します。
1. 10まで数えましょう

これは指を使った頭の体操です。「あれ?」と思わず声が出て、場が温まりやすいゲームです。やり方はとってもシンプル!
-
片手の親指を曲げた状態からスタート
-
1~10を声に出して数えながら、片手は親指から、もう片方の手は人差し指から1本ずつ指を曲げていく
-
「10!」になったとき、①と同じ状態であればクリア!
「できた方は、今度は逆の手の指を折るところから始めてみてください。」
📌 心理士として使ってみて実感したこと
このゲームは、スライドや資料がない場面でも口頭の説明だけで十分伝わる手軽さが魅力です。
実際にやってみると、できそうでなかなかできない絶妙な難しさがあって、つい夢中になっちゃいます。また、2本の指を曲げた状態から始めるなど、レベルアップが自由にできるのが面白いポイントです。
私の講義や研修でも、アイスブレイクが終わった後にこっそり指を動かして練習している参加者がいるほど、ハマる人が多い印象です。初めての場面でも場が盛り上がりやすく、誰でも気軽に参加できるので、アイスブレイクとしてとてもおすすめです。
2. ちぐはぐゲーム

紙とペンがあればすぐできるゲームです。やってみると意外と難しくて、「え?」という声が上がりやすいです。
-
「ごめんね」と言いながら紙に「ありがとう」と書く
-
「しろくま」と言いながら紙に「くろまめ」と書く
-
「プリッツ」と言いながら紙に「ポッキー」と書く
📌 心理士として使ってみて実感したこと
「言う言葉」と「書く言葉」の文字数が一致すれば何でもOK。反対の意味や似た言葉を使うと、さらに混乱して面白いです。
「せーの!」のタイミングで、みんなで同じ言葉を言いながら書くと、自然と一体感が出てきて、わいわい楽しくなります。ただ、周囲の人と直接関わる必要がないので、人とのやりとりが苦手な方でも安心して参加できるのが、このゲームの良いところです。私は、午後の研修や、難しい内容が続いたあとのタイミングで、リフレッシュを目的に取り入れることが多いです。
頭を切り替えるきっかけになったり、ちょっとした笑いが起きたりして、場の空気がふわっとやわらかくなるのを感じます。
3. 魔法の薬指

このゲームは、ちょっとした“手品”のような要素があり、参加者同士で「なんで!?」という驚きや笑いを共有できるのが魅力です。
- 左手をパーに開く。
- 右手の親指と人差し指で、左手の親指をつまむ。
- 左手の人差し指から小指に向って、指を一つずつ1から5まで数えながらつまむ。
(小指まで来たら方向を変えて、薬指に戻る)
👉 この時点で、薬指をつまんでいる状態。 - 頭の中で好きな数字を思い浮かべる。
- 再度、親指側・小指側どちらの方向でもOKなので、好きな数字の分だけ数えながらつまむ。
- もう一度、繰り返す。(数字は変えない!)
- 小指側に向って「2」を数えながらつまむ。
- さぁ、今どの指をつまんでいますか?
📌 心理士として使ってみて実感したこと
「好きな数字を自分で決めたはずなのに、なぜか同じ指になる」ことに驚いて、本当に合ってるのか何度も確認してしまいました。
実はこれ、どんな数字を選んでも必ず薬指にたどり着くようになっているんですが、初めての人にはまるで手品のように感じられて、とても盛り上がります。2回ほど繰り返すと、会場がざわざわし始めて、「なんで!?」という声や笑いが自然と広がっていきます。
うまくいっても、うまくいかなくても「えっ?」と反応が出やすいので、緊張感のある空気をやわらげたいときにもぴったりです。ただし、やり方の工程がやや複雑なので、口頭だけで説明するよりも、スライドや図を見せながら進めるとわかりやすいです。
その分、参加者の集中をグッと引きつける力もあるので、「今ここに注目してほしい」というタイミングで使うのもおすすめです。話さずにできるのに、参加者同士で驚きを共有できる、ちょっと不思議で楽しいアイスブレイクです。
4. 後出しじゃんけん

このゲームは、簡単そうに見えて意外と混乱する、後出しじゃんけんを使ったアイスブレイクです。
研修や講義の中で、「新しい習慣」や「新しい視点」を伝える導入としてもぴったり。
-
「私に勝ってください」と言って、じゃんけんで後出ししてもらう
-
次は「私に負けてください」と言って、じゃんけんで後出ししてもらう
- 徐々にスピードを上げていく。
📌 心理士として使ってみて実感したこと
このゲームは、勝つのは簡単だけど、わざと負けることに慣れていない参加者が多く、戸惑いながらも楽しんで取り組む様子が見られます。
「慣れないことは難しいけど、練習すればできる」というメッセージを自然に伝えられるので、新しい習慣や視点の導入にぴったりだと感じています。また、シンプルなルールながら意外と頭を使うため、研修の最初や途中に取り入れると場がやわらぎ、集中しやすい雰囲気づくりに役立ちました。
5. いくつかけるかな?

紙とペンさえあればすぐできる、シンプルだけど楽しい頭の体操ゲームです。
-
「ロ」という漢字を紙に書く
-
「口」に2画足してできる漢字をできるだけ多く書く(例:四、田)
-
制限時間内(3分程度)に何個書けたか競います。
【答え】
四、四、目、田、白、古、占、召、叱、加、石、右、
申、台、虫、由、只、旬、甲、旧、旦、兄、号、叶、可、司・・・
📌 心理士として使ってみて実感したこと
このゲームはルールがシンプルなのに、参加者が自由に発想を広げられるのが魅力です。
「田」などは思い付きやすいけど、「虫」など意外な字はなかなか出てこず、参加者からは「え?!そっちに2画足すのもありなのー?!」と驚きの声がよくあがります。
こうした驚きや発見が場を盛り上げ、発想を広げたいときや視点を変える導入としてとても効果的だと感じました。また、短時間で場が和み、笑顔や驚きが自然と増えていく様子も印象的です。
頭を使うことに集中することで、研修の合間の気分転換になり、次の内容への切り替えがスムーズになるのも実感しています。
まとめ:アイスブレイクで場をやわらげるコツ
今回は、参加者が一人でできるアイスブレイク・ゲームを5つ紹介しました。
どれもシンプルだけど、場の空気をやわらげるために工夫された内容ばかりです。
それぞれのゲームについて、心理士として実際に使ってみた感想も合わせてお伝えしましたが、どのゲームも参加者が自然に楽しめる工夫や驚きがあり、研修や講義の中で気軽に取り入れやすいのが特徴です。
ゲームを通して参加者がリラックスし、笑顔が増えることで、研修の雰囲気がぐっとよくなるのを実感しています。
また、単に場を温めるだけでなく、「新しい視点を受け入れる」「慣れないことに挑戦する」など、学びや気づきにつながる要素も取り入れられているので、研修の目的にも合いやすいと思います。
もちろん、すべてのゲームがどんな場面でも万能というわけではありません。参加者の特性や研修の内容、雰囲気に合わせてゲームを選び、アレンジしながら使うことが大切です。
今回紹介したゲームを知っておくことで、急に「場が固いな…」と感じた時や「参加者の緊張をほぐしたい」と思った時にも、すぐに対応できるようになるはずです。
ぜひ気軽に取り入れて、研修や講義をより良いものにしていってくださいね。
次回は、複数人で楽しめるグループ向けのアイスブレイク・ゲームを紹介します。
そちらもあわせてご覧いただければ嬉しいです。
この記事が、皆さんの臨床でお役にたてると幸いです。