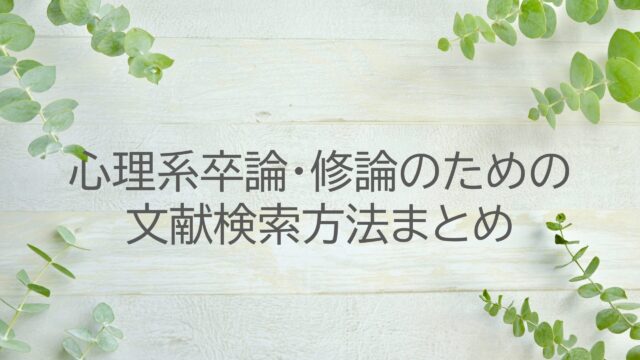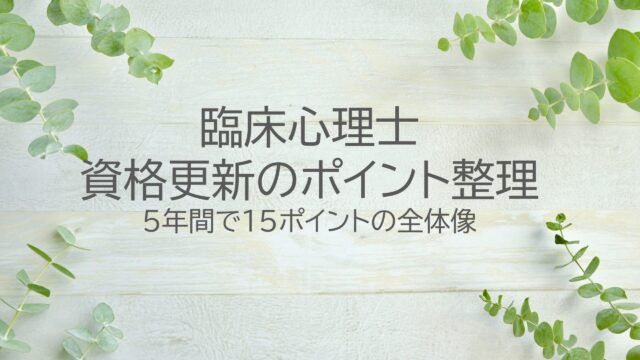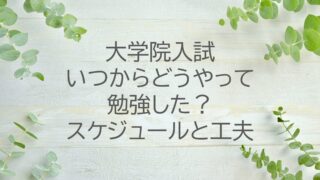【心理士1年目向け】おすすめ学会・入会タイミングと費用のリアル
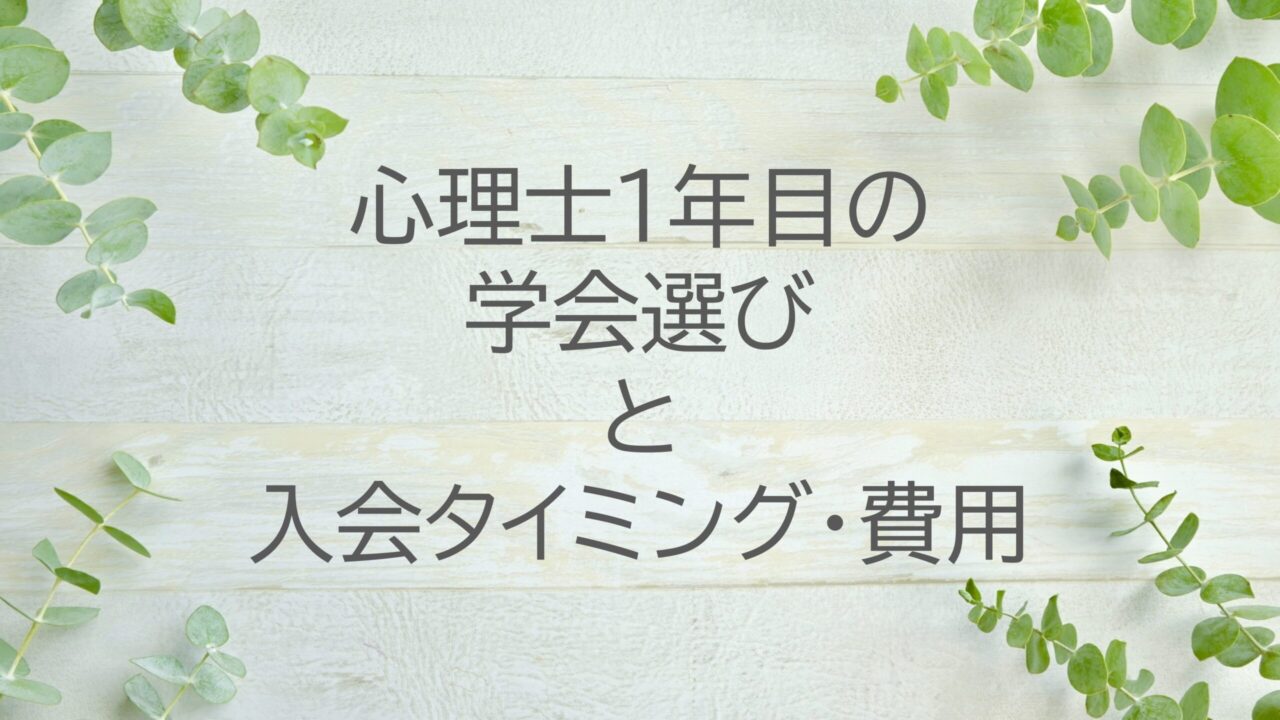
心理士として働きはじめたけれど、「学会ってどう選べばいいの?」「入る意味あるの?」「費用が…」という迷い、ありませんか?
私自身も大学院在籍時、そうした疑問を感じていました。

特に学生や若手の方は、学会がどのようなものか、入会するとどんなメリットがあるのか、そもそもどうやって入会するのか、わからないことだらけかもしれません。
この記事では、私自身の大学院時代から1年目までの経験をふまえて、心理職としての学会選びに役立つ視点や情報をまとめてみました。お金やタイミングの話も含めてお伝えします。
※本記事は、筆者自身の経験をもとに、学会選びの考え方や一般的な情報を整理したものです。
各学会の最新情報や入会条件については、必ず公式サイトをご確認ください。
学会に入ると、実際どんなメリットがあるの?
「学会って、論文発表をする研究者が入るところでしょ?」
そんなイメージを持っている方もいるかもしれません。
もちろん、研究者にとって論文発表や情報交換の場であることは間違いありません。
しかし、それ以外にも多くのメリットがあります。
最新情報のキャッチアップ
学会誌やメーリングリストを通じて、その分野の最新の研究動向や知見を知ることができます。
個人的体験談
特に、メーリングリストでは職域関連の時事情報やニュース、求人情報や研修案内、書籍の割引販売のお知らせ等、多様な情報が得られるので、私は重宝しています。
スキルアップの機会
学術大会や研修会に参加することで、実践的なスキルや知識を深めることができます。
個人的体験談
日心臨(日本心理臨床学会)では年に1回の大会とは別に、地区研修会がオンラインワークショップ等も開かれています。私は以前、描画テストやCBTのワークショップに参加したことがあるのですが、翌日からの臨床に役立つ事柄を体験的に学ぶことができ、とても良い機会になりました。その時の資料はいまでも大事に保管しています。
人脈づくり
同じ分野の研究者や臨床家と出会い、情報交換や共同研究の機会を得られます。
個人的体験談
ポスター発表等は特に、その発表者と直接話をすることができます。私は院生の時に、自分の関心のある領域のポスター発表を聞きに行ったら、発表者の方も院生でした。研究の話とは別に、院生生活についての情報交換をすることができたのも良い経験です。余談ですが、そんな時のために、名刺は持ち歩いておくことをお勧めします。
資格維持に役立つ(臨床心理士の場合)
臨床心理士は、指定された研修や学会活動に参加することで、資格更新のためのポイントを取得できます。
個人的体験談
臨床心理士の資格更新のためには、5年以内に下記の①から⑥の教育研修機会に、①②のいずれかを含めた3項目以上にわたって参加(発表)し、計15ポイント以上を取得することで資格を更新できる仕組みになっています。
(参考:臨床心理士資格認定協会)
①資格認定協会が主催する研修会等への参加
②日本臨床心理士会もしくは地区又は都道府県単位の当該臨床心理士会が主催して行う研修解答への参加
③資格認定協会が認める関連学会での諸活動への参加
④資格認定協会が認める臨床心理学に関する研修会への参加
⑤資格認定協会が認めるスーパーヴァイジー経験
⑥資格認定協会が認める臨床心理学関連の著書の出版
多くの方が①+②+③、①+②+④、①+③+④、のような組み合わせでポイントを取得することが多いように思います。学会に参加しないと3項目以上にまたがってポイントを取得できない、と言っても過言ではありません。私はこれまでの更新で、①+②+③+④の組み合わせで申請していました。
このように、学会はあなたのキャリアをサポートしてくれる重要な存在です。

学会の選び方に迷ったら、こう考えてみよう
心理系の学会は数多くありますが、すべてに入会する必要はありません。
どの学会に入るかは、自分の関心のある領域や活動スタイルによって決めていくとよいでしょう。
ステップ1.関心のある分野の年次大会に非会員資格で参加してみる。
一般社団法人 日本心理学諸学会連合のサイトには、学会大会の情報の一覧が掲載されています。
https://jupa.jp/category2/syogakkai.html
この一覧からまずは、気になる学会を検索してみると良いでしょう。
複数の学会に参加してみると、学会ごとの特色や、参加者の雰囲気も体感的に感じることができます。
多くの学会は非会員でも大会に参加できる制度を設けているため、自分にあっているかどうかを見極める良い機会になります。
また、非会員参加の場合は年会費を払う必要がないため、年間費用を抑えられるのもメリットです。
学部生の方であれば、時間に余裕があるうちに足を運んでみるのも良い経験になります。
いきなり入会せず、まずは非会員で年次大会に出席してみましょう。
コラム:学会会場の出版社ブースを活用しよう
学会会場では、各出版社がブースを設けて関連書籍を販売していることがよくあります。その領域に関連した書籍が集められているため、最近の動向を把握するのに役立ちます。学会に参加したら、ぜひ出版社ブースも訪れてみてください。新しい発見があるかもしれません。

ステップ2.臨床心理士資格取得後に検討すべき2つの職能団体
「日本臨床心理士会」 か 各都道府県の「臨床心理士会」のいずれかを検討しよう。
臨床心理士資格を取得したら、まずは「日本臨床心理士会」と各都道府県の「臨床心理士会」のいずれか、または両方への入会を検討しましょう。
これらはいずれも臨床心理士登録後に入会が可能です。
私の記憶では、合格通知と一緒にこれらの入会案内資料が同封されていたと思います。
日本臨床心理士会(以下、日本士会)と各都道府県の臨床心理士会(以下、県士会)は学会というよりは、臨床心理士の実務を支える“職能団体”という位置づけです。
日本士会も県士会も資格更新時のポイント取得に関わる研修情報や倫理サポートなど、実務に役立つ情報を提供しています。
ちなみに私は日本士会と県士会の両方に加入しています。
県士会は、地域でのつながりを作る上でも重要です。
各都道府県によって会費や活動内容が異なるので、公式サイトをチェックしてみましょう。
日本臨床心理士会のサイトを開けば、各地の士会の一覧を見ることもできます。https://www.jsccp.jp/area/
資格更新ポイントを意識しよう
臨床心理士資格は5年ごとに更新があります。
その際に必要な「研修ポイント」は、
日本士会または県士会に所属していないと加算できない研修が多くあります。
どちらか一方には所属しておくと安心です。
日本臨床心理士会 入会のメリット
- 日本臨床心理士会雑誌の発行、メールマガジンの配信
- ホームページ内の会員専用ページの利用(研修会出席履歴、求人情報掲示板、など)
- 賠償責任保険など、総合補償制度の提供(業務上のリスクヘッジとして大きな安心材料になります)
- 日本臨床心理士会が主催する研修会等の情報提供
- 臨床心理士の職能に関する最新情報の提供
(出典)一般社団法人日本臨床心理士会 入会案内ページより
各都道府県臨床心理士会 入会のメリット
- 居住地都道府県内での研修のため、研修会場が近く、交通費や宿泊費を抑えられる
- 学会参加に比して低価格で研修が受けられる
- 同一領域の人とのつながりを作りやすい
- 研修参加が臨床心理士の更新ポイントになる。
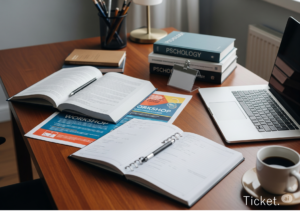
個人的体験談
私が両方の士会に入ってるのは、それぞれで入会のメリットを体感しているからです。
・日本士会の個人的メリット
-賠償責任保険に加入できる
-日本各地の求人情報が得られる
-研修情報が得られる
・県士会の個人的メリット
-研修会場が県内で行われるため、参加しやすい
-近隣地域の動向を知ることができる
-格安で研修が受けられ、ポイントにもなる
日本心理臨床学会への入会について
心理系の学会は多数ありますが、日本心理臨床学会(以下、日心臨)は心理臨床の主要学会であり、年次大会や学会誌、研修情報など、実践的な学びの機会が豊富に用意されています。
そのため、ここでは日心臨を例に入会のタイミング・入会方法について紹介します。
入会のおすすめタイミング
学会への入会にはタイミングも大切です。
どの学会も年会費制のため、入会時期によっては数か月で次年度の会費が発生することもあります。
以下におすすめの入会タイミングを整理しました。
日心臨は大学院在学中から入会できます。
日心臨の場合(2025年度現在)、
- 入会金 :10,000円
- 年度会費:9,000円
- ※大学院在学中の方は、入会金免除+年会費5,000円(2025年度時点)
つまり、大学院在学中に入会すると費用面でも有利です。
入会方法(見落としがちなポイント)
日本心理臨床学会の入会には、現会員2名の推薦が必要です。
多くの場合、指導教員や実習先の臨床心理士が推薦人となります。
そういう点でも、指導教員や実習先の先生に相談しやすい在学中の入会が好機です。
オンライン申請も可能になってきていますが、書類の準備や推薦依頼など、少し時間がかかることもあるため、余裕をもって準備しましょう。
お金やスケジュールはどのくらい?
学会への入会・継続には、年会費の支払いがつきもの。
多くの学会では、年に一度(多くは4月)に口座振替またはクレジットカードで年会費が引き落とされます。
たとえば、以下のような費用感になります(2025年時点の目安):
| 学会名 | 年会費 | 備考 |
|---|---|---|
| 日本心理臨床学会 | 学生5,000円 / 正会員9,000円 |
入会金あり (院生の場合は入会金不要) |
| 日本臨床心理士会 | 8,000円 | 資格登録後に入会 |
| 都道府県士会 | 約5,000~10,000円 | 地域により異なる |
年度末(2~3月)は就職・引っ越しなどで出費が増える時期でもあります。
年会費が一気に引き落とされる4月に備えて、事前にスケジュールと予算の見通しを立てておくと安心です。
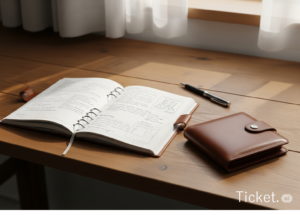
まとめ:あなたの学会選びの「困った」を「大丈夫」に変えるために
心理士1年目の学会選びは、分からないことばかりで不安に感じるかもしれません。
しかし、この記事でご紹介したポイントを押さえることで、あなたがこれからの学会選びを、より安心して進められると嬉しいです。
迷いをなくし、スムーズな一歩を踏み出すための3つのロードマップ
- まずは「お試し参加」から!年次大会で雰囲気を掴もう
関心のある学会の年次大会には、まず非会員で参加してみるのがおすすめです。実際の雰囲気や、どんな人が集まっているのかを肌で感じ、入会後のミスマッチを防ぎましょう。費用を抑えつつ、情報収集できる賢い第一歩です。
(参考:各学会大会の情報はこちらから確認できます ≫ 日本心理学諸学会連合) - 【費用もお得に】院生のうちに「日本心理臨床学会」への入会を検討しよう
心理臨床の主要学会である日心臨は、大学院在学中に入会すると入会金が免除され、年会費も割安になります。実践的な学びの機会も豊富なので、キャリアの土台作りに大きく貢献します。
(詳細はこちら ≫日本心理臨床学会入会方法) - 【資格更新も安心】臨床心理士会は資格取得後の早期入会がおすすめ
資格取得後すぐに「日本臨床心理士会」と「都道府県臨床心理士会」のいずれか、または両方への入会を検討しましょう。資格更新に必要な研修ポイントが効率的に取得できるほか、賠償責任保険などの安心材料も得られます。
(日本士会のメリットを再確認 ≫日本臨床心理士会)
学会は、あなたのキャリアを豊かにしてくれる場所です。
この記事が、自分の興味や実務に合った学会と出会い、キャリアを築いていく上での安心材料になりますように。ぜひ参考にしてみてくださいね。