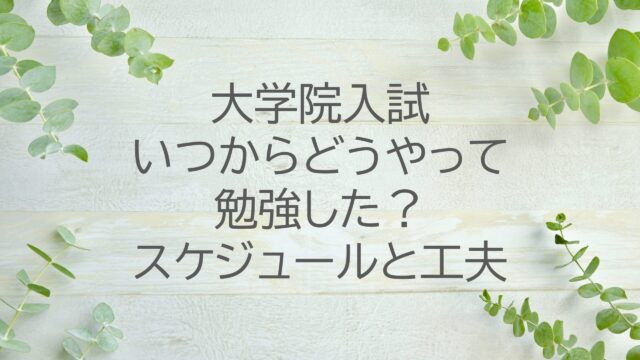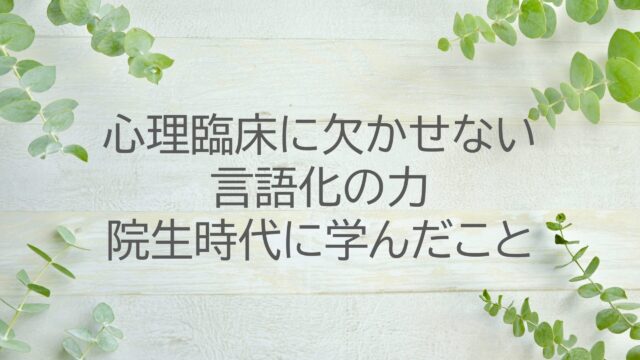心理職のセルフケア|緊張と緩和のバランスを保つためにできること

心理職として働く中で、緊張を感じる場面は少なくありません。
初めての出勤、初めての緊急支援――そんな“初めて”が続く時期は特に、心と体の緊張状態が続きやすくなります。
この記事では、筆者自身が体験した「初出勤」と「緊急支援」のエピソードをもとに、緊張と緩和のバランスを保つための工夫について考えていきます。
初めての体験に緊張するのは自然なこと
初めてのことを体験するとき、緊張してしまう
――そんな経験は、きっとどなたにもあるのではないでしょうか。
過度な緊張は、肩凝りや頭痛など、体にさまざまな影響を及ぼすことがあります。
そして、ふっと緊張がほどけた時、肩の力が抜けるのを感じたり、体の内側がじんわり温かくなるのを感じたりしたことはありませんか?
極度の緊張状態が続くと、力の抜き方がわからなくなり、まるで止まり方を知らないランニングマシンを走り続けているような状態に陥ることもあります。
止まらないランニングマシンを走り続けるとどうなるでしょうか。

気づかないうちに体は酷使され、ついには突然倒れてしまう
――そんな状況は想像に難くありません。
では、そうならないために、心理臨床の現場で長く安定して働き続けるには、どんな工夫が必要なのでしょうか。
それは、まず「緊張と緩和のバランスを意識する」ことから始まると考えています。
今回はそのことを学んだ私の実体験を2つご紹介します。
Episode1.初出勤の日
大学院を修了して社会人1年目を迎えた4月1日。
初めての出勤日、
私は朝何時に出勤するのが正解なのか分からず、念のため、始業20分前に職場に到着しました。
ところが、さすがに早すぎたようで誰もいません。
一人で職場の前に立ち、誰かが来られるのをじっと待っていると、最初の出勤者がやってこられました。
別部署の方で、私がどこに居たらよいかわからず、その方も対応に少し戸惑っている様子でした。
申し訳ない気持ちになっていると、少しずつ出勤する人が増え、同じ部署の上司が現れ、「あら、早いね」と声をかけてくださり、少しほっとしました。
その日は、前任者からの引き継ぎ資料の確認や事務手続き、関係部署への挨拶まわりなどで
あっという間に過ぎていきました。
特に厳しい人がいたわけでも、放っておかれたわけでもないのに、私は必要以上に緊張していたと思います。

退勤して職場を出た瞬間、
「あ、私、今日丸一日ずっと緊張してたんだ」
と強く実感しました。
胸がぎゅーっと締め付けられたような感覚に気づき、「この締め付けは一旦解放しなくては」と思いました。
結果、その日は駅までの道を歩きながら、
人知れず涙しながら帰ったことを、
今でもよく覚えています。
Episode2.初めての緊急支援
ある日、私はある学校での緊急支援を任されることになりました。
前日の夜、学校から連絡が入り、翌朝からの対応を依頼されました。
初めての緊急支援だったため、私は『学校コミュニティへの緊急支援の手引き』を何度も何度も読み返して準備しました。
当日の朝、緊張しながら現地へ向かい、業務に従事しました。
養護教諭への報告を終え、帰路についたとき、駅を降りて自宅までの道のりで、初出勤のときと同じような胸のつまりを感じました。
緊迫した業務の中、初めての緊急支援で「前夜からずっと緊張していたんだな」とあらためて気づきました。
ぐっと我慢することも考えましたが、やはり「一旦緩めねば」と思い、駅から自宅までの道を歩きながら、涙を流して家路につきました。
緊張と緩和の体験から学んだ2つのこと
心理臨床に携わっていると、緊張を伴う場面は決して珍しくありません。
しかし、ずっと緊張し続けると、冒頭でお話したように、いずれか限界が来てしまいます。
長く安定してこの仕事に従事していくためには、以下の2点が大事なように思っています。
- 自分の状態を自覚できておくこと
- 緊張の高まりを感じた時には適宜緩める作業ができること

意図的に緩める時間を取り入れよう
この記事を読んで、「もしかすると自分も力が入りすぎているかも」と思われた方は、
ぜひ意識して適度に緩める時間を取り入れてみてください。
今回は「涙を流す」という方法を例に挙げましたが、緩め方は泣くことに限りません。
- ヨガや呼吸法
- 温泉につかる
- 軽いストレッチ
- 自然の中を散歩する
- 信頼できる人との会話
等、いろいろなアプローチがあります。
ご自身にあった方法を探してみてください。
緩め方のレパートリーを増やしておくと、心と体のバランスを保ちやすくなると思います。
まとめ
緊張は、責任感の表れでもあります。
しかし、その緊張を抱え続けることは、心身にとってリスクとなる場合もあるのです。
心理職として働き続けるためには、緊張と緩和のバランスをとる意識と実践が欠かせません。
「頑張りすぎていないかな?」「少し緩めてもいいのかも」と感じたときは、ぜひ自分自身をいたわる時間を持ってみてください。
- 窪田 由紀・林 幹夫・向笠 章子・浦田 英範・福岡県臨床心理士会(2005).学校コミュニティへの緊急支援の手引き.金剛出版.
- 福岡県臨床心理士会・窪田 由紀(2020).学校コミュニティへの緊急支援の手引き(第3版).金剛出版.
- 有田 秀穂(2007).涙とストレス緩和.日薬理誌,129,99-103.https://www.jstage.jst.go.jp/article/fpj/129/2/129_2_99/_pdf(2025年5月30日取得).
- 高路 奈保・中野 友佳理・満居 愛実・上利 尚子・有安 絵理名・吉村耕一(2015).情動性の涙のストレス緩和作用に関する研究.ストレス科学研究,30,138-144.https://www.jstage.jst.go.jp/article/stresskagakukenkyu/30/0/30_138/_pdf(2025年5月30日取得).