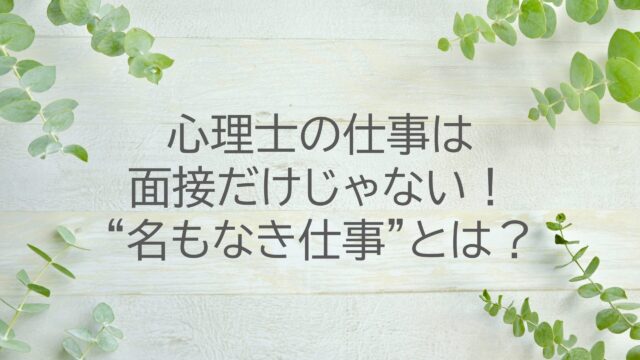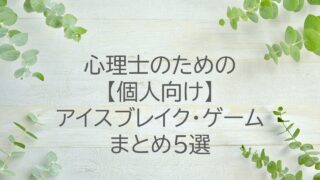研修や集団療法に!心理士のためのグループ向けアイスブレイクゲーム3選
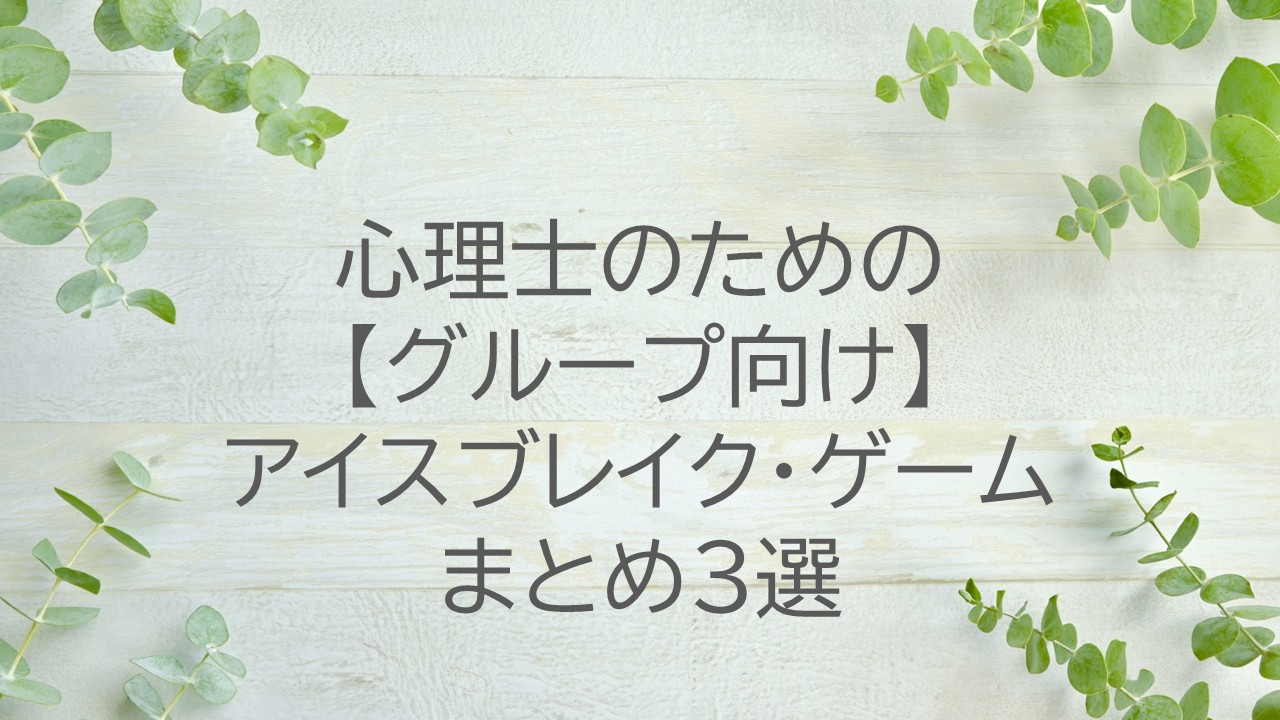
そんなとき、アイスブレイクはとても頼りになる味方です。緊張した空気をゆるめ、参加者同士の関係づくりを助けてくれます。
前回の記事では、参加者が1人でできる【個人向けアイスブレイク】をご紹介しました。
アイスブレイクの基本的な役割や、選ぶときの視点については前回の記事にまとめていますので、そちらもぜひご覧ください。
この記事では、グループで行うアイスブレイクのネタ3選と心理士として使ってみた感想をご紹介します。
参加者同士が声を出したり協力したりしながら、自然と関係性が築かれていく内容になっています。いくつか知っておけば、咄嗟の場面でも使えますし、1つのゲームを少し変えるだけで何通りにも応用できます。
研修や集団療法の導入や合間の時間など、場に合わせてぜひ取り入れてみてくださいね。
※研修や集団療法で使用する際は、参加者の特性や場の目的に配慮し、無理のない範囲で取り入れてください。
アイスブレイク、ゲームの選び方とタイミング

アイスブレイクを使うタイミング
アイスブレイクを「いつ入れるか?」を考えるとき、
私はまず、
「何のためにそのアイスブレイクを入れるのか」
「参加者にどんな体験をしてほしいのか」を意識しています。
その目的によって、ベストなタイミングやゲームの選び方は変わってきます。
ここでは、私がよく使うシーン別に、タイミングと意図をご紹介します。
研修初回、研修冒頭
第1回目の研修。
場の空気が緊張した状態になっていると思います。
これでは参加者も研修担当者も居心地が悪く、
どんなに良い内容の研修を用意していても、学びが深まらないかもしれません。
そんな場の空気を和ませるために、安心感を生むためのアイスブレイクを行うようにしています。
たとえば、うまくいってもいかなくても楽しめるような、反応を自然に共有できるゲームがあると、場がやわらかくなりやすいです。
食後の時間帯
昼食後は、どうしても眠気が出やすい時間帯。
参加者が眠そうにしていると、研修担当者としてはちょっと不安になりますよね。
そんなときは、“リフレッシュ”を目的にしたアイスブレイクを取り入れます。
空気が軽くなるような、リフレッシュした感覚になりますよ。
難しい内容が続いたあと

法律や制度、専門用語など、頭を使う内容が続いたあとは、
会場全体に「重たい空気」が流れることもあります。
このときは、“気分転換”としてのアイスブレイクを入れると、場がパッと切り替わります。
次の内容への切り替えがスムーズになりますよ。
グループワークの前
いきなりディスカッションやグループワークに入ると、グループ内に緊張が残ったまま進んでしまうことがあります。
そんなときは、“関係づくりの土台”になるようなアイスブレイクを1つ入れるのが◎。
ゲームを通じて軽く話したり、一緒に何かをする体験があると、
その後のやりとりがスムーズになりやすいと思います。
どのアイスブレイクを選ぶか

アイスブレイクは、「いつ」「何の目的で」行うかによって、最適なものが変わります。
たとえば、研修の初回なら、多くの参加者は初対面同士。
「いきなりグループで話すのはちょっと…」という人も多いです。
そんなときは、あまり話さなくても参加できるタイプのゲームから始めるのが安心です。
最初に抵抗感のあることを体験してしまうと、その後の研修全体のモチベーションにも影響してしまいます。
その場の目的や空気感に合わせて、
「どれくらい人と関わるゲームか」、「どんな気分になれるゲームか」を意識して選ぶのがコツです。
アイスブレイク・ゲーム、ネタ3選(グループ編)
では、具体的にグループで行うアイスブレイク・ゲームを3つご紹介します。
手順・説明が簡単な順番でご紹介しますので、研修の時間やタイミングで使い分けてみてくださいね。
NOT30!

設定した数字を言ってしまった人が負け!というシンプルなカウントゲームです。
やり方
- じゃんけんをする
- じゃんけんで勝った人から時計回り
- 1人1~3つまで数字を順番に言う(1つでも2つでもOK)
- 順番に数を言って、最後に30を言ってしまった人が負け
📌 心理士として使ってみて実感したこと
このゲームはルールがとてもシンプルで、初対面同士のグループでも導入しやすいのが特徴です。
「何個言ったっけ?」と混乱したり、30が近づくドキドキ感をみんなで共有できるので、自然と場が和みます。
自己紹介や意見交換の際は、「30を言ってしまった人からどうぞ!」と流れを作るとスムーズです。またメンバー数によって数字を50に変えたり、「ABC」・「あいうえお」・「干支」などでアレンジすると、さらに楽しめます。
指定しりとり

やり方は通常のしりとりと同様です。
あらかじめ決められた最初と最後の単語に、どれだけ早くたどり着けるかを競います。
紙とペンがあると記録しやすく、勝敗も明確になるのでおすすめです。
やり方:
- 最初と最後の単語を伝える(例:最初いちご、最後きりん)
- グループで1人ずつしりとりをつなげていく(紙に書いていく)
- 最後の単語に早くたどりついたチームが勝ち!
例:いちご→ごりら→らっぱ→ぱんだ→だるま→マイク→くじびき→きりん
📌 心理士として使ってみて実感したこと
しりとりはルールがとてもシンプルなので、説明いらずで誰でもすぐに始められるのが魅力です。初対面でも構えず参加でき、「このゲームならできそう」と安心感を持ってもらいやすいのもポイントだと感じています。
実際にやってみると、「“ん”がついちゃうよ〜!」、「“ご”の次は何がある?」といった軽いやりとりが自然に生まれて、場の緊張がほぐれていくのを感じます。最近では「AIに聞こう!」と冗談を言う人もいて、笑いが関係づくりのきっかけになっていることも多いです。
勝敗がつくことがプレッシャーになりそうなときは、隣の人と相談してもよいと伝えるなど、場の雰囲気を見ながら柔軟に対応しています。
さらに、固定化しやすいしりとりに、「この言葉は禁止!」といったNGワードを設定するアレンジを加えると、ゲームに工夫が生まれて一層盛り上がります。たとえば、「“ら”で始まる言葉は禁止」とすると、よく使われる言葉を避けようとする過程で、自然に協力したり話し合う雰囲気が生まれます。
しりとりは、自分のことを話す必要はなくても、言葉のやりとりを通してグループに一体感を生みやすいので、初対面でのウォーミングアップにとても使いやすいゲームだと感じています。
聖徳太子ゲーム

一度に複数の話を聞いたとされる聖徳太子にちなんだ、リスニング力が試されるゲームです。ルールがやや複雑なため、スライドなど視覚資料があるとわかりやすいと思います。
やり方:
- 4~6人グループを作る。
- グループの中から1人、聖徳太子役を決める。
- 聖徳太子以外のメンバーが同時に言葉を発する。
- 聖徳太子役はできるだけ多くの単語を聞き取る!
📌 心理士として使ってみて実感したこと
このゲームは勝敗を競うものではないので、聞き取れた・聞き取れなかったに関わらず、みんなで楽しい体験を共有しやすいのが特徴です。また、このゲームは、うまくいくことのほうがむしろ珍しくて、たいていは聞き取れなくて笑いになる、というのがいいところです。だから、完璧にやろうと気負う必要がなくて、過度な緊張を感じにくいようです。
また、自己開示を求められず、個人の性格や価値観に深く踏み込む要素がないため、初対面どうしでも安心して取り組めます。話すのが苦手な人や、まだ距離のある相手とも、自然に笑いながら同じ体験を共有できるゲームだと思います。実際にやってみると、誰かがすべて聞き取れたり、まったく聞き取れなかったりすることで「今のすごい!」「全然わかんなかった〜!」といったやりとりが生まれて、そこから少しずつ会話が増えていくのを感じました。
最初の緊張をほぐし、安心感を醸成するための、ちょうどいいウォーミングアップとして、すごく使いやすいゲームです。
まとめ

いかがでしたか?
今回はグループでできるものを3つ紹介しました。
ゲームはあくまでも場の雰囲気を和らげるするためのツールです。
細かい手順にこだわらず、場の空気が少しでも和やかになるように
参加者の居心地がよくなるような、あたたかい雰囲気づくりにアイスブレイクを活用してみてくださいね。
この記事がみなさんの臨床でお役に立てますと幸いです。