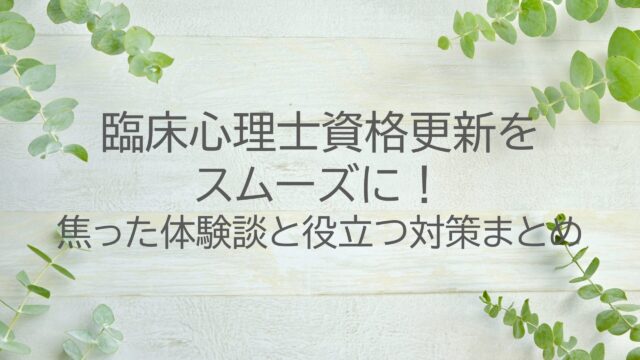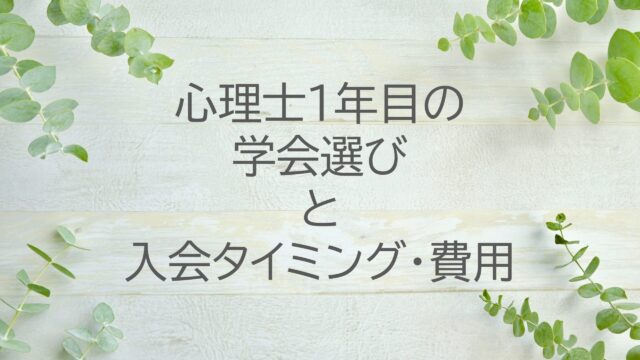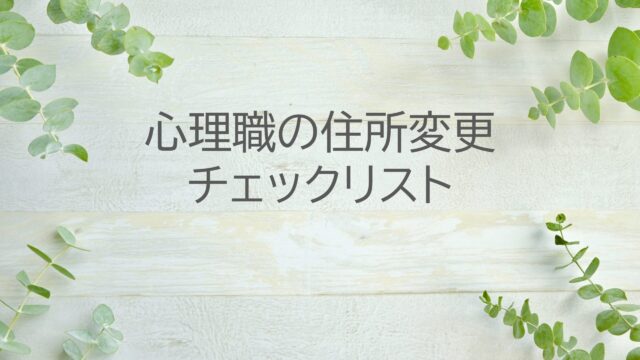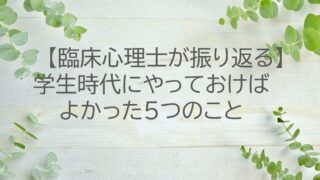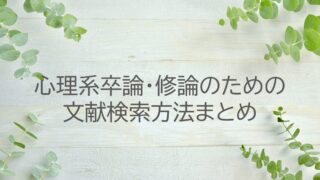臨床心理士資格更新のポイントを整理|5年間で15ポイントの全体像
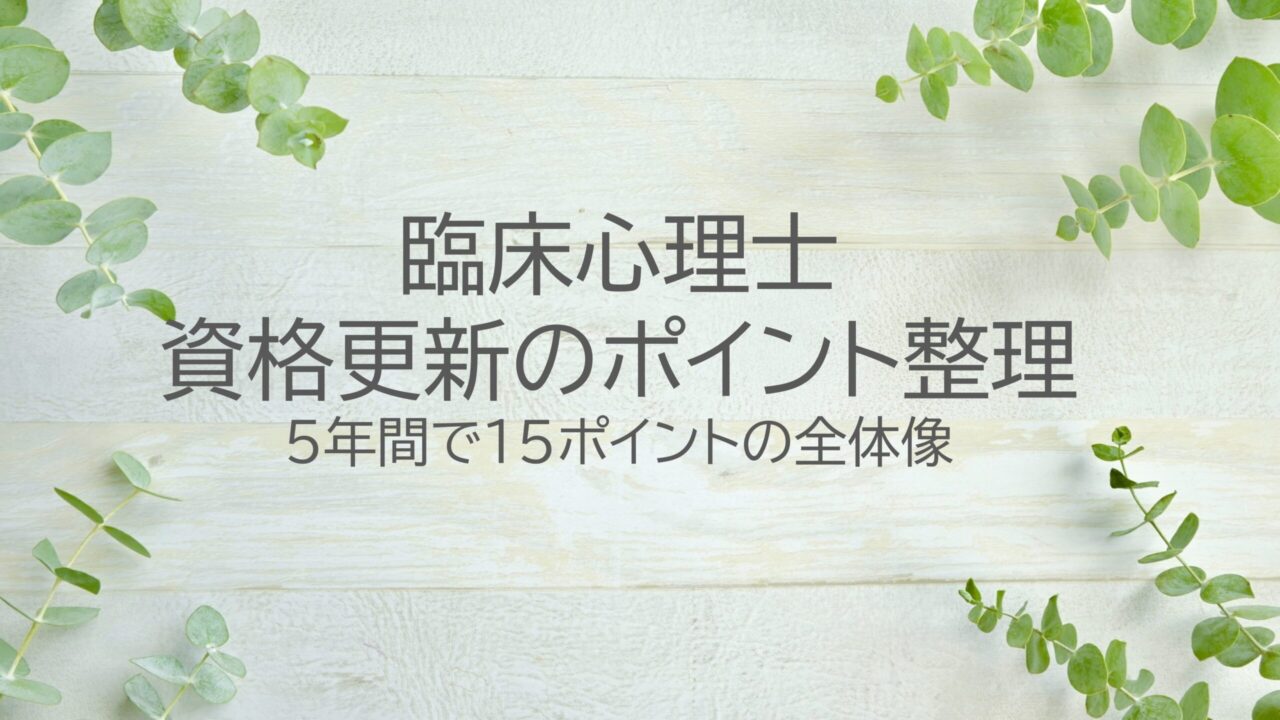
臨床心理士として活動を続けていくためには、資格更新が欠かせません。
更新には研修への参加を通じた「ポイントの取得」が求められます。
初めて更新に取り組む方にとっては
「どのくらいの研修に参加すればいいの?」
「効率よくポイントを集めるには?」
と疑問に思う場面も多いのではないでしょうか。
この記事では、5年間で15ポイントを無理なく、そして確実に取得するための戦略と、研修選びのコツをご紹介します。
※資格更新の制度や取り扱いは変更されることがあります。最新情報は必ず日本臨床心理士資格認定協会の公式案内をご確認ください。

資格更新の基本ルール:15ポイントと3つの領域
まず、臨床心理士の資格更新には、5年間で合計15ポイントの取得が必要です。
さらに重要なのが、この15ポイントは「3つの領域」にまたがって取得しなければならないというルールです。
領域には、以下の6種類があります。
- 資格認定協会が主催する研修会等への参加(臨床心理士研修会、心の健康会議)
- 日本士会又は都道府県士会主催の研修会への参加
- 資格認定協会が認める関連学会での諸活動への参加(日心臨他)
- 資格認定協会が認める臨床心理学に関する研修会への参加
(申し込み時点で資格ポイント申請予定の案内があるか要チェック) - 資格認定協会が認めるスーパーヴァイジー経験
- 資格認定協会が認める臨床心理学関係の著書の出版
上記の6領域のうち、5年以内に①②のいずれかを含めた3項目以上にわたって参加(発表)しなければなりません。
そして、5年間で15ポイントということは、1年あたり平均3ポイントの取得が目安となります。
年に1、2回、何かしらの研修に参加する意識を持つだけで、ぐっとハードルは下がります。
各領域の細かなポイントの設定については、資格認定協会のHPをご確認ください。

研修選びの第一歩:ポイント取得可否の確認を怠らない
「せっかく研修に参加したのに、ポイント対象外だった…」という悲劇は避けたいものです。
研修に申し込む際は、必ず研修案内文を隅々までチェックしましょう。
③領域、④領域の研修については、「臨床心理士資格更新ポイント申請予定」や「申請中」といった記載があるかを事前に確認することが鉄則です。
この確認を怠らなければ、無駄な研修参加を防ぎ、効率的なポイント取得が可能になります。

日常的なポイント取得の柱:日本心理臨床学会(日心臨)の活用
5年間で15ポイントを確実にクリアするための最も効果的な戦略は、毎年開催される日心臨の年次大会に継続的に参加することです。
日心臨の年次大会は領域③に該当します。
1回参加するごとに2ポイント付与されます。
5年間で毎年参加すれば、それだけで10ポイントが貯まります。
これは全体の3分の2を占める大きなウェイトです。
日心臨は、最新の知見や研究に触れる貴重な機会であるだけでなく、ポイント取得の観点からも非常に効率的です。
もし、参加が難しい年があっても、オンラインでの参加など柔軟な選択肢が増えているので、積極的に活用しましょう。
残りのポイントをどう取るか?:心の健康会議と県士会研修他
日心臨で10ポイントを確保したとしても、残り5ポイントを集める必要があります。

心の健康会議
「心の健康会議」は5年のうちに1回は参加しておきたい研修です。
これも更新ポイントの対象となり、出席すれば確実にカウントされます。
会議は全国各地で開催され、5年間のうちに少なくとも1度は居住地近隣で開かれるタイミングがあります。
その時期を狙って申し込みをすると効率的です。
ただし、近年は参加希望者が多く抽選漏れするケースも増えています。
確実にポイントを確保するためにも、「参加できたらラッキー」くらいの気持ちで、他の研修と並行して計画しておくのが安心です。
県士会(都道府県臨床心理士会)の研修
心の健康会議の代替案として心強いのが、県士会の研修です。
多くの県士会が研修会を主催しており、1回の参加で2ポイントが取得できます。
心の健康会議が抽選に外れた場合や、近隣での開催がない場合に、県士会の研修に1回参加しておけば、確実に2ポイントを確保できます。
スーパーヴィジョン(SV)や専門研修
さらに、スーパービジョンを受けることでポイントを取得できる仕組みもあります。
日常の実践を振り返りながら学びを深められるため、更新対策だけでなく臨床力の向上という意味でも有効です。
また、自分の関心のある専門領域の研修に参加してポイントを得るのも良いでしょう。
最近はオンラインセミナーを開催してくださる機関が増えてきた印象があります。
特に、オンデマンド配信のセミナーは子育て世代の心理士には大変ありがたい強い味方です。
そうしたオンラインセミナーも活用したいですね。
実際のモデルケース:これで安心!ポイント取得シミュレーション
これまでのポイントをまとめ、具体的なモデルケースを見てみましょう。
ここでは、発表者・シンポジスト・論文発表・論文執筆・著書出版の予定がなく、基本的に参加者(受講者)の立場のみでポイントを取得しようとした場合の例をご紹介します。
モデルケースA:最もスタンダードな取得パターン
日心臨への継続的な参加を軸に、心の健康会議と県士会の研修を組み合わせていく最も安定したパターンです。
- 領域①心の健康会議に1回参加:2ポイント
- 領域②県士会の研修に1回参加:2ポイント
- 領域③日心臨に毎年参加:2ポイント× 5回 = 10ポイント
- 領域③or④の関心あり研修に1回参加:2ポイント
合計16ポイント
モデルケースB:SVを活用した取得パターン
日心臨への継続的な参加を軸に、SVee経験を組み合わせたパターンです。研修参加の2ポイントに対してSVは3ポイントと取得できるのがおすすめ。SVの申請方法についてはこちらの記事をご参照ください。
- 領域②県士会の研修に1回参加:2ポイント
- 領域③日心臨に毎年参加:2ポイント×5回=10ポイント
- 領域⑤個人的なSVee経験:3ポイント
合計15ポイント

まとめ:計画的な参加がスムーズな更新につながる
計画的に取り組むことが大切
資格更新は5年に1度ですが、「まだ時間がある」と油断していると、直前に慌てて研修を探すことになりがちです。
毎年コツコツと研修に参加し、ポイントを積み重ねておけば安心して更新を迎えられます。
特に、日心臨のように毎年開催される大きな学会を基盤にして、残りを県士会や心の健康会議で補うスタイルは、多くの心理士が実践している方法です。
資格更新を学びの機会として活用しよう
臨床心理士の資格更新は、計画的に行動すれば決して難しいものではありません。
- 日心臨に毎年参加すれば10ポイントが確保できる。
- 残りの5ポイントは、心の健康会議や県士会の研修、あるいは関心のある個別研修で補っていくのが現実的。
- 研修の申し込み時には、ポイント取得の可否を必ず確認。
この道しるべを参考に、5年間の研修計画を立ててみてください。
まずは今年の参加可能な研修をリストアップし、カレンダーに記入することから始めてみましょう。
資格更新のための研修が、自身の学びを深め、臨床家としての成長を促す貴重な機会となることを願っています。
臨床心理士資格更新をスムーズに!焦った体験談と役立つ対策まとめ
SVが臨床心理士資格更新のポイントになる!手順をご紹介
【心理士1年目向け】おすすめ学会・入会タイミングと費用のリアル